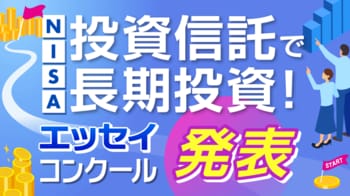まず、株式や投資信託を買う人は増えているのか? に着目してみる
まず、気になるのが株式や投資信託を買う人が増えているのかどうか、という点でしょう。直近まで、S&P500や日経平均株価が最高値を更新し続けてきただけに、家計部門がどの程度、リスクオンになったのか、注目されるところです。
家計部門の金融資産保有残高の推移を見ると、投資信託は2024年を通じて前年比30%前後で増加していますし、株式等についても投資信託には及ばないとしても、安定的に前年比増を続けています。
とはいえ、これらの保有残高は時価評価になっているので、マーケットが上昇すれば、その評価益によって金額は押し上げられますし、逆にマーケットが下落すれば、評価損が生じることによって金額は押し下げられます。
したがって、実際に資金が流入しているのか、それとも流出しているのかを見定めるためには、この評価損益分を取り除いた数字を見る必要があります。
そのために必要なのが「調整額」の数字です。この調整額がマイナスの時は評価損が生じているので、実数を把握するためには、この評価損分を残高に加えます。逆に調整額がプラスの時は評価益が発生していることになるため、実数を把握するためには、この評価益分を残高から差し引かなければなりません。
このようにして調整した残高で推移を見ると、株式に関しては2024年9月以降、資金流入ペースが落ちています。2023年9月期から2024年6月期までの前年同期比は20%台で増えていましたが、2024年9月期以降は伸び率が1ケタ台になり、2024年12月期と2025年6月期の前年同期比はマイナスになっています。
これはおそらく、株価の動きと関係しています。2023年9月期から2024年6月期までは、日経平均株価が3万1000円台から過去最高値を更新し、4万円台をつける過程でした。また2024年9月期以降、2025年6月期までは、株価がボックス圏で推移しています。つまり株価の上昇局面では資金流入が大きく伸び、逆にボックス圏の時には資金流入ペースが大きく落ちることが分かります。
では投資信託ですが、こちらは安定的に伸びています。2023年9月期以降、2025年3月期まで、前年同期比は15~33%の増加です。投資信託の場合、NISAの積立投資枠の影響があるのかどうかは定かでないものの、恐らく積立購入の普及が、安定した資金流入を支えているように思えます。