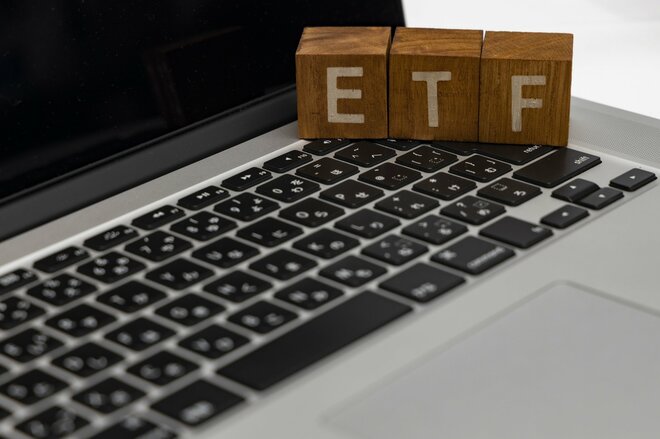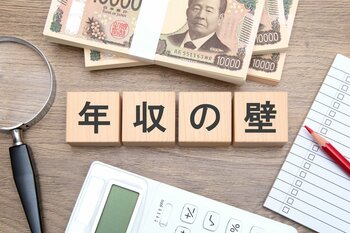東京証券取引所が「アクティブETF」の上場を解禁したのが2023年6月のこと。同年9月7日に6銘柄が同時に上場して以降、日本株、米国債、J-REITを投資対象とする計19銘柄が登場してきた。
そして9月10日に、20本目にして初のグローバル株を投資対象とするアクティブETFが上場した。ブラックロック・ジャパンの「iシェアーズ AIグローバル・イノベーション・アクティブETF(愛称:ベストAI)」がそれだ。
従来、ETFといえば「インデックス型」のイメージが強く、それはアクティブETFの上場が解禁されて2年超が過ぎた今でも、あまり変わりはない。インデックス型とは、日経平均株価やTOPIX、S&P500といった指数などに連動する仕組みを持つETFだ。それに対してアクティブETFは、特定の指数に連動した投資成果を目指す商品とは異なり、運用会社やファンドマネジャーが、運用方針に沿って投資・取引対象や資産配分を選定する。
米国アクティブETF市場の急成長
残高や銘柄数、さらに革新性……あらゆる面で世界のETF市場をリードする米国で初めてアクティブETFが登場したのは、2008年。その歴史自体は長いが、特に2019年の規制変更を契機に、上場本数、残高とも急速に伸び始めている。米国の証券市場には現在、約4300本のETFが上場しているが、今年6月にはアクティブETFの上場本数がインデックス型のそれを上回り、大きなニュースにもなった。現時点の残高ベースではアクティブ型は全体の1割程度にとどまっているが、銘柄数やマーケット全体の流入額を占める割合、ETFプロバイダーの顔ぶれ、商品ラインアップの多様性といった面では、急速に存在感が増していると言えるだろう。
アクティブETFの3つのタイプ
アクティブETFのいちばんベーシックな定義は「連動対象となる指数が存在しない」ことだが、それをタイプ別に分類するとどんな整理ができるのだろうか。ブラックロック・ジャパンのプロダクト・ソリューション部でETFチームの責任者を務める東條健一氏は「アクティブETFは大まかに、エクスポージャー型、アウトカム型、アルファ追求型という3つのタイプに分けられます」と説明する。

エクスポージャー型は、債券や経済発展が初期段階にあるフロンティア諸国の株式など、市場規模や各種規制などにより市場の流動性が極めて限られた資産クラスにアクセスを提供するタイプだ。資産クラスそのものの流動性が低く、対象インデックスへの精緻な連動が容易ではない場合でも、アクティブETFであれば組成が可能となる。アクティブETFにそれらを組み入れて上場すれば、流通市場内では間接的に流動性を高めることができる。
アウトカム型は、オプションなどのデリバティブ手法を用いて、収益や損失をコントロールするものが主体であり、「目標設定型」と言い換えることもできるだろう。
たとえば損失を一定の範囲内に抑制するバッファ型と呼ばれるものや、組入資産の値上がり益の一部を犠牲にする代わりに、高いインカム収入を確保するカバードコール型などがその中心を占めている。
そしてアルファ追求型は、最もアクティブらしいアクティブETFといってもいいだろう。調査・分析にもとづく銘柄選択・投資配分などにより、市場全体または特定のベンチマークを上回る実績を目指すETFで、今回、ブラックロックが上場したベストAIも、この分類に入る。
これら3タイプのうち、近年、大きく伸びているのが、アルファ追求型とアウトカム型だという。
そもそも米国では、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)や、RIA(登録投資助言業者)といったアドバイザーが顧客ニーズに応じたポートフォリオを構築・提案する際に、コスト面や品ぞろえ、税制面でアドバンテージのあるETFをツールとして積極的に活用している。彼らの報酬体系が、商品提供時のコミッション(販売手数料)ではなく、顧客から預かった資産残高に応じたフィーベースの料率になっているためだ。コストや税金も考慮した自らの提案によって顧客の残高が増えれば増えるほど、自身の報酬も増大する構図である。
アドバイザーが顧客に高付加価値なポートフォリオ提案を行ううえで、市場平均を上回るリターンを狙うアルファ追求型や、リスク抑制や利回り向上を目指すアウトカム型のアクティブETFを選好し、そのニーズに応えるべくETFプロバイダー各社がこぞってラインアップの多様化を進めることで、アクティブETF市場のエコシステムが生まれている。
もっとも、アドバイザーによる需要だけが市場拡大のけん引役ではない。ETF市場には誰もがアクセスできるため、個人が直接アクティブETFを選択し、ポートフォリオを市場環境に即してチューンアップすることも自在だ。
「従前から、カバードコールなどの戦略を組み込んだファンドは機関投資家向けに提供されていましたが、それをアクティブETFとして組成したことにより、小口資金を運用する個人にも手軽に使えるようになりました。特に近年米国では、S&P500が値上がりしたことにより、配当利回りが低下しています。そのためS&P500で運用している人たちが、自分たちの運用利回りを改善させるために、ポートフォリオの一部をアウトカム型のETFに配分して運用するケースも見られるようになってきました」(東條氏)。