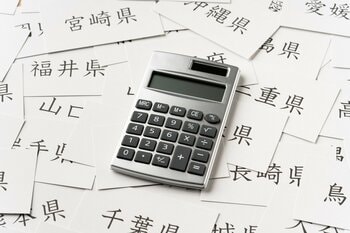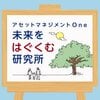毎月分配型が NISAの対象とならなかった背景
改めて、現在のNISA制度についておさらいをしてみます。
NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠があり、年間の投資限度額は、それぞれ120万円と240万円で、合計360万円となっています。また、生涯投資枠というのがあり、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて1,800万円が上限となります。
NISAで投資できる投資信託には、主に次のような制限があります。
つみたて投資枠では、国内や海外の株式に投資する株式型ファンドか、株式を含みつつ、債券やREIT(不動産投資信託)などにも投資するバランスファンドで、その多くがインデックス型となります。
そして、購入時手数料は無料、運用時に掛かる信託報酬は指定されたインデックスに連動するファンドであれば、国内資産は年率0.5%以下、海外資産であれば年率0.75%以下の水準とされています。
また、成長投資枠では、信託期間が無期限または20年以上あるもの、決算頻度が毎月ではないもの、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託ではないもの、とされています。
この「決算頻度が毎月でないもの」というのが「毎月分配型」を指します。
ここで、決算頻度という言葉が出てきましたが、投資信託法は会社法に準拠しており、投資信託は年1回以上の決算を行うことが義務付けられています。そして、その決算時に株式会社が配当を行うように、分配金を払い出すのです。決算頻度は、年1回、年2回、年4回、年6回、年12回の投資信託があります。
現行NISAでは、年6回(隔月)決算の投資信託は対象となりましたが、年12回(毎月)決算の投資信託は対象外になりました。
一般的に分配金が払い出されると、その分、投資信託の純資産総額が減少し、再投資を行うと足し戻されます。しかし、その分配金が実現益によるもの(普通分配金)だと、譲渡益課税(20.315%)を差し引かれた後に足し戻されることになるため、複利効果が得られにくく、その分確実にリターンが低下することから、分配頻度の高い投資信託は長期投資に向かないと言われているのです。
よって、2024年から始まったNISAでは、毎月分配型が対象外になったというわけです。
また、毎月分配型には信託報酬の高いものも多くありました。特に通貨選択型のように為替ヘッジを行うものは外国の投資信託に投資をする仕組みにするため、国内の投資信託と合わせて信託報酬の二重取りのようなことが起こり、信託報酬が高くなる傾向がありました。
しかし、将来的にNISAの対象となる毎月分配型は、デリバティブ取引を使っているものが除外されるでしょうし、信託報酬に上限が課されるなどされる可能性が高いのではないかと思われます。
また、金融庁も高齢者が安心して利用できるように金融機関からの情報提供を強化したり、分かりやすい説明を義務付けるのではないかと思います。