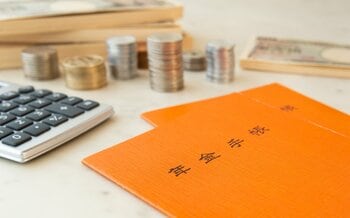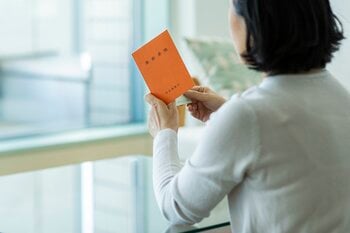公的年金にとって外国人は「貢献度大きい」
会合では国立社会保障・人口問題研究所の林玲子所長が登壇。「少子化及び外国人労働者の動向と年金財政」と題して基調講演を行いました。
日本の出生率は、2005年から2015年にかけて微増が見られたものの、その後は低下しています。少子高齢化が深刻化する中、一部では、外国人が日本で子どもを産むことで、結果的に出生率の減少が食い止められるのではないかとの期待論があります。
ただ、林氏は、フランスなど他国と比べて、受け入れた外国人が入国後に出産する割合が少ないことや、そもそも日本へ送り出す国(中国、韓国、タイなど)の出生率が日本よりも低くなっている現状を指摘し、外国人増加による出生数改善は見込みにくいことを説明しました。
また、日本での外国人の「出生力」が低い原因については、婚外子の権利・選択的夫婦別姓を含め結婚や出生をめぐる規範・制度が欧米などと比べ著しく前時代的であるといった課題を挙げました。
一方、現在の公的年金制度についてみると、外国人の多くは被用者であることから、厚生年金への外国人の加入は203万人に上る一方、国民年金は加入者が自営・留学生に限られ、77万人にとどまっています(いずれも2025年3月時点)。
外国人労働者が自ら払った分は将来的に本人に一時金として戻ることになりやすいものの、企業が払った部分は年金基金に入ります。林氏はこれを踏まえ、「現時点では受給要件を満たす前に帰国する者が多いと考えられ、年金制度に対しては中立ないしは貢献度の方が大きい」との考えを示しました。
それでは今後、外国人の人口増加は公的年金財政にどのような影響を与えるのでしょうか。林氏が紹介した先行研究(2015年発表)では、低賃金の男性労働者を政策的に毎年10万人受け入れると仮定して、「外国人労働者のみを受け入れる」(ケースA)と、「家族の帯同・呼び寄せや第2世代以降の誕生などを前提とする」(ケースB)の2パターンに分けてシミュレーションを実施。その結果、ケースAでは、社会保障負担の大きさを示す一つの指標となる老年従属人口指数(生産年齢人口に対する老年人口の割合)に当初、一定の低減効果がみられるものの、外国人もまた年々高齢化していくため、長期的に見れば効果が薄まっていくことが示されました。
一方の外国人だけでなくその家族も受け入れるケースBでは、来日した本人が高齢化したとしても第2世代以降の誕生があるため、老年従属人口指数の「低下幅もより大きい」といいます。