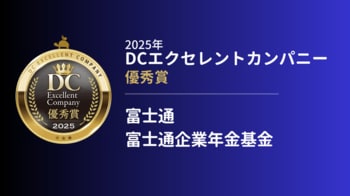近年、人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営が注目されている。その観点からも企業年金の一つである企業型確定拠出年金(DC)制度の充実は、従業員の活躍やエンゲージメントを高める一因として企業価値の向上に資することが期待されている。企業型DC制度運営に熱心な企業はどのような取り組みを行い、そしてどんな成果を実現しているのか。DC制度運営に秀でた企業に贈られる「2025年DCエクセレントカンパニー」継続教育部門において優秀賞に輝いた新宮運送の取り組みを紹介する。
企業型確定拠出年金(DC)における継続投資教育では、関心の低い加入者へのアプローチが大きな課題となっている。新宮運送では、個別面談の実施や確定拠出年金お助け隊の結成など、中小企業ならではの"顔の見える距離感"を活かしたサポート体制を構築。結果、元本確保型の残高比率は58.3%から30.1%まで大幅に減少するなど、着実な成果を上げている。
制度導入時の課題は加算拠出への抵抗感
当社の退職金制度は、中小企業退職金共済(中退共)とDCの二本柱です。以前は適格退職年金に加入していましたが、運用利回りなどを鑑み、2006年に中退共に移行。その後、2014年にDCを導入しました。
DC導入のきっかけは、法人契約をしていた生命保険の担当者から、「DCは大企業では採用され始めているが、中小企業ではまだあまり取り入れられていない」と話を聞いたことです。社内で検討したところ、DCは社員の老後資金準備を支援できる制度で、会社側にもメリットがあるという結論に至り、導入を決めました。
制度の運用を始める前には社員に向けて説明会を行い、社長からも「DCはみなさんが老後に備えるための制度。会社から掛金の拠出を行い、自身の給与から上乗せもできる」と導入までの経緯と想いを伝えました。その際、中退共は“退職時にもらえる給付金”、DCは“前払いの退職金”といったイメージで、二本柱で老後に備えていく重要性も強調しました。
当初は加入者に投資信託を選んで、加算拠出を行ってもらうことで、老後資金を最大化してほしいと考えていました。しかし、ここで最初の課題にぶつかります。実際に制度の運用を始めると、加算拠出する加入者がほとんどいなかったのです。事前説明で制度への理解を促したものの、実際の行動には結びつかず、加入者の理解が表面的なものにとどまっていたことを痛感しました。