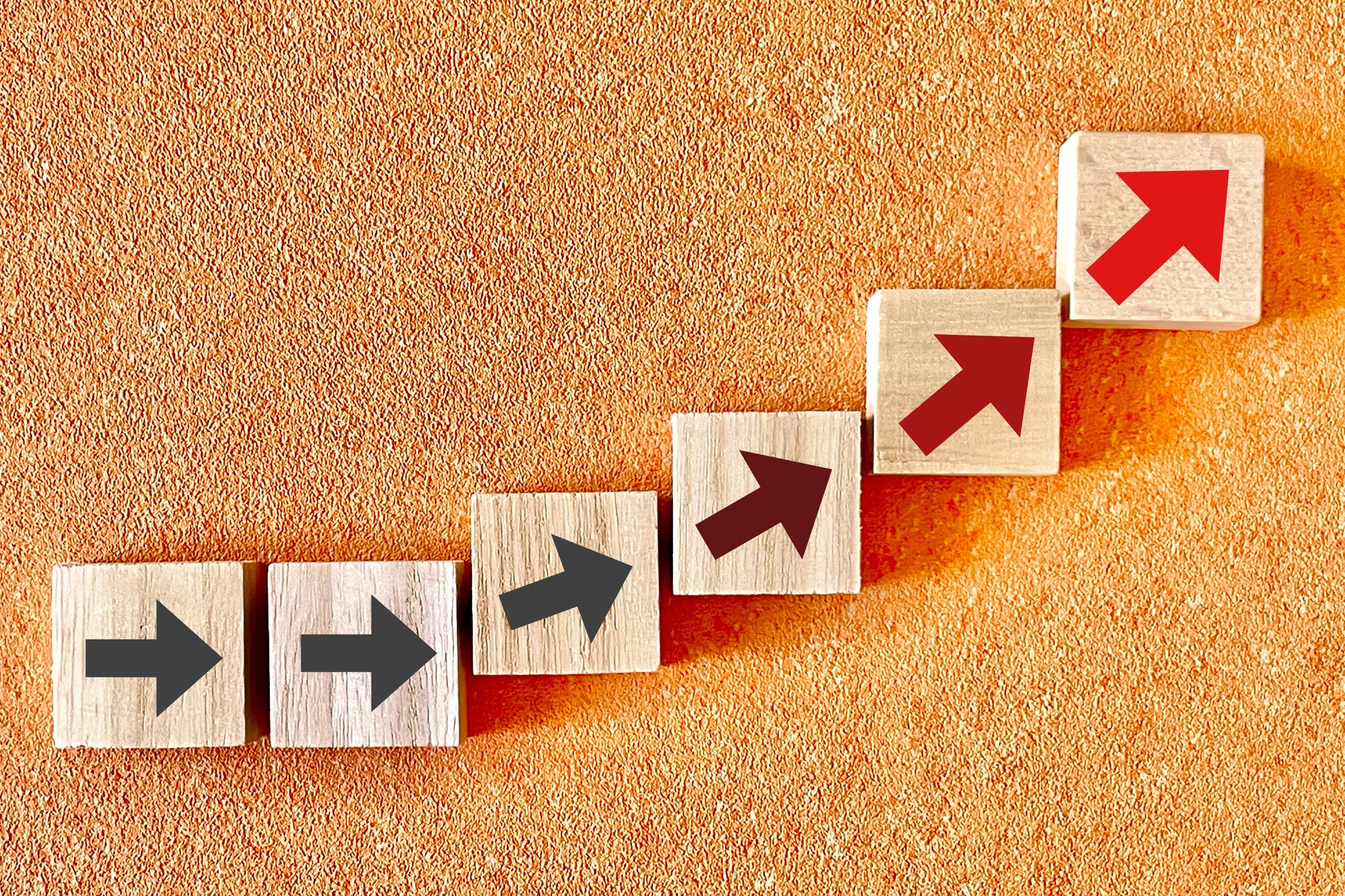分配頻度は「毎月」から「隔月」か?
中国銀行の売れ筋上位ファンドの特徴の1つは、分配金の頻度が高いファンドが目立っていることだ。地方銀行の投信顧客の中心は高齢層が中心で、年金生活にプラスアルファの生活資金として投信の「分配金」に期待している傾向は強くあるだろう。運用しながら取り崩すことによって、保有資産の寿命を延ばすという考え方は広く行き渡っている。ランキングトップの「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」が運用成績の良しあしに関わらず、毎月1万口当たり150円の分配金を継続しているのは、そのような投資家ニーズに応えた仕組みともいえる。
一方、「One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)」や「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」は、隔月決算にすることでNISA成長投資枠の対象となり、かつ、運用成績に応じた分配金の金額になっている。NISAの対象となることで分配金に課税される20%の税金が免除され、かつ、投資元本を削るような無理な分配金を出さないために資産の寿命は一段と延びる。
多頻度決算を好む投資家にとって、理想は予想分配金提示型でありながら、安定的な分配金が継続できるファンドだろう。そのためには、安定的にファンドの基準価額が上昇し続ける運用成績が必要になる。それは、誰もが望む投信の運用成績にも通じている。どのような投資対象を、どのような運用方針で運用すれば安定的に資産の成長が実現できるものなのか、運用会社の模索はずっと続いている。
執筆/ライター・記者 徳永 浩