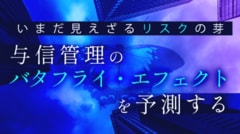2-1. 「ハイスペック」の定義が変わってきた
①スキル ②知識 ③経験を豊富に有した人材は、これまでもいわゆる「ハイスペック人材」として重宝されてきた。
しかし「技術の腕」「知識量」「経験年数」といったわかりやすい能力値だけで打開できる仕事は価値が下がってきている。我々がITを使い倒すことで皮肉にも、そうした能力は「ヒトでなくても代替できる」ものになり、今の人材は「ITやロボができることの更に上を行く」思考や着想・行動が求められるようになってきた。
ダボス会議では、定期的に「未来の人材」をうたっているが、これを見るといかに要求水準が高度化し、定量化が難しくなっているか、が一目瞭然だ。
2022年以降に不要となる能力
(世界経済フォーラム「仕事の未来レポート2018」より)
1位 手先の器用さ、持久力、精度
2位 記憶力、言語能力、聴覚能力、空間能力
3位 財源の管理
4位 テクノロジーのインストールとメンテナンス
5位 リーディング、ライティング、数学、アクティブリスニング
2025年に必要となる能力
(「仕事の未来レポート2020」より)
1位 分析的思考と革新
2位 アクティブラーニングと戦略的学習力
3位 複雑な問題解決能力
4位 批判的思考と分析
5位 創造性、独創性、イニシアチブ
かつての「ハイスペック人材」でも、「英語は堪能だが、交渉力はイマイチ」や「MBAホルダーだが、経営手腕は頼りない」など、①スキル ②知識 ③経験のピースだけでは十分でないことは薄々感じられていた。加えて時代が変化し、その人ならではの発想や行動が期待されるようになった。それゆえ①~③の価値の比重が低下しており、スペックに拠った人材定義は形骸化している。
2-2. ピースの“隙間”にも着目することが第2のカギ
実は、1-3で述べた「ケイパビリティの分解」には続きがある。①スキル ②知識 ③経験に加え、以下のような要素も考慮する必要がある。
④行動:ジョブに必要な考え方・動き方の特性(変えることができるもの)
⑤資質・感性:ジョブに活かせる考え方・動き方の特性(④行動と類似するが、より個人が根本的に保有しており変えづらいもの)
例えば「プロジェクトマネジャー(PM)の認定資格を複数持っており(①スキル②知識)、前職では複数のプロジェクトでPM経験を務めてきた(③経験)」という「知識・スキル・経験」を備えた2名が採用され、プロジェクトリーダに任命されたとしよう。1か月後、1名は「常に顧客志向でサービス品質に高い責任感を持ち、それらを前向きなメッセージに変換して周囲の行動を牽引している(④行動)。また、人の深層心理の把握・理解に長けており、顧客の傾向を捉えたリスク管理やメンバーのモチベーション維持といったチーム構築にも成功している(⑤資質・感性)」。一方、もう1名は「理論・知識に基づいて正確ではあるものの杓子定規な判断や行動が目立つ(④行動)。ぶれない決定基準は持っているが状況に応じた柔軟性に欠ける(⑤資質・感性)ため、非連続な問題が発生する中でプロジェクトは停滞している」
解像度の低い人事や現場の目線で言えば、前者は、いわゆるバランスの取れた優秀層、後者は社内の経営者選抜から漏れていく層といったところだろう。誤解されがちだが、これらもスキル・知識に類する「ケイパビリティ」の一つとして、言語化されるべきである。そして後者が必ずしも劣性というわけではない。適したロールを付与することで成果が変わる要素であり、こうしたピースの隙間ともいえる部分まで精度を上げておけるかどうかで、必要なケイパビリティを持ったより多くの人材を結果につなげることができるのである。
2-3. 従業員価値の見落とし
これで今度こそ、完璧なジョブディスクリプションが出来上がるだろうか?ここまでに述べたケイパビリティの構成要素①~⑤は、ある種、“やらされ”人事から脱却するための組織目線の要求事項であった。しかし、これだけで従業員側も変わることができるのだろうか?従業員の意識としては、いつまでも「会社に指示され、都合のいいコマとして扱われる」 受動的な意識から抜け出せず、自立的に成長するプロフェッショナルとはいえないのではないだろうか?
「DX人材育成」に鋭意取り組もうと、スキルや知識のみならず、行動や資質も含むケイパビリティを定義しようとした先進的な企業においてもつまずくポイントがここだ。「従業員にとっての価値が見落とされている」ということである。「ケイパビリティ」の内訳として、最後に1つだけベクトルが異なる要素を取り挙げたい。
⑥アスピレーション(個人の好奇心、志)である。
これは個人が物事に対して本質的な興味・関心を持ち、自ら追求していこうとする行動の源泉を指す。ここが組織の目指す方向性とマッチしていないと、どんなに外から働きかけても従業員は成長せず、いつまでも「やらされ感」で終わってしまう。
これまでのように組織や事業戦略のために会社が従業員を選び、従業員は選ばれることを運に任せる流れを逆転させる必要がある。従業員が自律的なキャリアを形成し、会社が機会を提供する。機会を求める場を提供できない会社は従業員から選ばれなくなるという視点を会社も認識する必要がある。
3-1. 双方が納得できる定義をつくる
DX人材の定義では、以下のステップを踏む必要がある。前回は下記の1~4を説明し、今回は下記の5~8までを説明してきた。
- ①事業戦略・成長戦略の分解
- ↓
- ②人材タイプの定義
- ↓
- ③現状把握、課題分析
- ↓
- ④人材ポートフォリオへの落とし込み
- ↓
- ⑤スキルの定義
- ↓
- ⑥ロールとの紐付け
- ↓
- ⑦レベル、キャリアパスの設計
- ↓
- ⑧従業員価値の定義
ポイントは、全ての定義にあらかじめ“従業員にとっての価値”を織り込むことである。例えば、人材タイプをスキル・知識・経験にブレイクダウンする過程であれば、「顧客」である従業員に幅広くヒアリングするなどのマーケティングを行うといったやり方が考えられる。
他にも行動・資質といったソフトを織り込む際には、実際にモデルとなる社員の顔触れを踏まえて議論する、ジョブディスクリプションには人事目線での要求事項のみならず、従業員のキャリアにとってどんな価値・経験をもたらすかまで明文化する、など常に個人のアスピレーションを念頭においた魅力づけを行うことで、従業員自ら成長するための選択やコミットが期待できる。
また、これらの定めた人材要件は後続のすべての人事プロセスに一貫して使われる。その各プロセスも従業員にとってポジティブな体験となるように設計しなおすことが必要である。採用や社内公募の際にはジョブディスクリプションだけでなく、先輩社員の動画を見せて将来のキャリアイメージをもってもらったり、育成においては上司やコーチとの1on1を通じて、自身のこれまでとこれからを棚卸す時間を作ったりする。配置においては自分のキャリアやプライベートな計画を踏まえ、拝命したロールといかに向き合うのかを周囲と共有しておく——など、いずれのイベントにおいても、組織と従業員との双方が共通の言語で語り、従業員の自己実現を組織が手助けすることで成長を促し、組織の成長にもつながる。
上記のアプローチ以外に急速に関心が高まりつつあるのは、AIを活用したスキル診断・管理ツールである。提供サービスは学習データとして社外の同等の人材像がもつスキルを取り込んでおり、自社の人材の労働市場における価値を確認するなどもできるようになってきている。AIの活用については今後取り上げる予定である。
3-2. 金融機関B社の例
今回も最後に国内金融機関の実例を見てみよう。この会社ではデジタル・システム分野の大半を外注していたが、内製化に舵を切ろうとしていた。そこで改めて必要な人材の解像度を上げて要件定義に取り組むことにした。
まず人材定義の範囲は「特に内製化すべき領域」であった上流工程と一部の開発領域を中心に絞り込んだうえで、①スキル②知識③経験を定義していった。「テクノロジー」ならば開発管理、アプリケーションエンジニア、ITアーキテクトに分けたうえで、開発標準の定義も活用して客観的に定義し得る事項を盛り込んだ。ただし「細かくし過ぎない」ようにした。区分やスキルを細分化し過ぎても逆に育成現場で持て余してしまい、時代に応じて変わるスキルに追加や修正が追いつかないといったことも懸念された。①~③はあくまでベーシックなものを最低限定義しておくことで、現場に浸透させやすいものとした。
④行動⑤資質・感性⑥アスピレーションは社内で活躍している人材や外注先の人材をベースに実感の湧く定義を徹底した。個別に判断が分かれる部分はその人材タイプの上位者が合議を通じて擦り合わせていくこととした。また社内の人材でキャリア要望が少ないタイプは内製を止めて外部委託で確保することにした。
実際に1on1を行ってみると、各従業員のキャリアイメージは人材タイプや具体的なスキルを特定して目標に設定されることよりも、実際に周囲に存在する優秀な人材に置き換えて「あの人のようになりたい」という反応が多い。過度に作り込んで実態と乖離することなく、組織や市場の期待値を受け入れるバッファを持っていることで、従業員自身が自然に選択し、成長する道しるべとして機能できている。