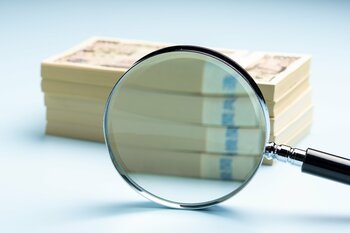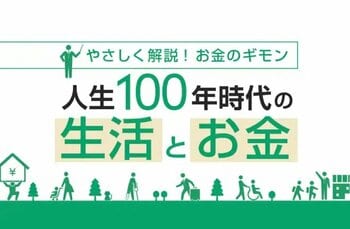いよいよ7月3日から新札が登場します。
1万円札は「近代日本経済の父」と言われた渋沢栄一。5000円札は日本人初の女性留学生で、津田塾大学の創設者である津田梅子。そして1000円札には「近代日本医学の父」と言われる北里柴三郎の肖像が用いられます。
発行開始が7月3日で、2025年3月末までには現在、用いられている紙幣の46%に相当する74億8000万枚が印刷される予定です。
新札登場は世の中に、どのような影響を及ぼすのでしょうか。
まず新札を発行する最大の目的は、偽造防止と言われます。新札が発行されてから一定の期間が経過すると、発行当初の偽造防止に関する技術力が陳腐化してしまいます。つまり偽造されやすくなります。そのため、紙幣は20年に1度くらいの頻度で新札を発行することにより、偽造防止を強化するのです。
まだ実物を手にしたわけではないので、一般的に報じられていることを引用しますが、今回の新札での偽造防止策としては、紙幣を斜めに傾けると肖像が立体に動いて見える最先端のホログラム技術が導入されているということです。
ちなみに偽造紙幣の発見枚数は、警察庁のウェブサイトで見ることができます。それによると、2023年を通じて発見された枚数は、
1万円札・・・583枚
5000円札・・・20枚
2000円札・・・0枚
1000円札・・・78枚
でした。あくまでも発見された枚数なので、実際に流通、あるいは退蔵されている枚数がどのくらいかは分かりませんが、過去の数字を見ると、偽造紙幣の枚数はだいぶ減っています。
1996年の発見枚数は152枚でしたが、1999年に3422枚、2000年に4257枚、2001年に7613枚と増え続け、2004年には2万5858枚まで増加しました。その後は減少傾向にあり、2020年には2693枚、2021年には2110枚、2022年には948枚、そして2023年には681枚となっています。
なぜ2004年にかけて偽造紙幣の発見枚数が急増したのに、直近にかけては減少したのでしょうか。警察関係者のコメントが6月4日の産経新聞に掲載されているので、それを引用します。
「1990年代から2000年代初頭にかけて、日本ではコンビニエンスストアや家庭でカラーコピー機が急速に普及。『手軽というと語弊があるが、安易なニセ札製造が相次いだ』(警察関係者)とされる」。
だそうです。そして、直近にかけてニセ札の発見枚数が減少傾向にあるのは、やはりQRコード決済をはじめとするキャッシュレス決済が普及したからでしょう。