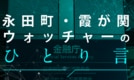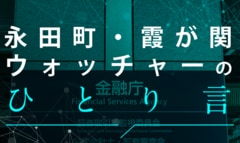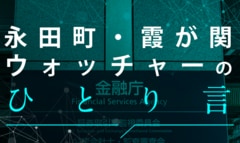プルデンシャル生命保険で明るみに出た一連の不祥事は、単なる営業担当者の個人的な業務行為の逸脱や偶然の出来事では片付けられない、根深い組織の病巣を私たちに突きつけた。なぜ、これほどまでに多くの顧客と職員が関与し、長期間にわたって深刻な事態が放置され、なおかつ内部からの異論が封じ込められてきたのか。こうした問いに真摯に向き合わない限り、いつまでも同じような過ちが、形や場所を変えて繰り返されることになるだろう。これは金融業界に身を置く誰にとっても、決して他人事ではない。
何をもって「成果」とするのか
不祥事が起きるたび、決まって槍玉に挙げられる「成果主義」だが、それ自体が悪なのではない。努力や創意工夫を正当に評価する仕組みは、活力ある組織運営に不可欠である。問題は、その「成果」の内容だ。
短期的な契約成立を「成果」と見なす評価制度は、営業員に目先の数字を追わせ、顧客の真のニーズから目を背けさせる誘惑を生む。
顧客本位を本気で追求するのであれば、その契約が顧客の人生に長期的な安心と価値をもたらし続けているかを「成果」と見なすべきだと思う。こうした理念を実現するには時間と手間を要し、即座に数字として表れないかもしれないが、顧客の人生を豊かにし、揺るぎない信頼を築くという、金融機関に求められる真の価値の創出につながるだろう。
顧客本位は、時間に耐える覚悟
顧客の人生は長く、金融商品の影響は時間差を伴って表れる。だからこそ、それに連動する評価や報酬もまた、時間の経過を織り込んだものでなければならない。
顧客本位とは、即座に答えが出ない行為であり、短期的な報酬とは本質的に緊張関係にある。
この時間の壁を乗り越え、真の顧客本位を実現するためには、少なくとも以下の三点が不可欠となる。
・アップフロント型報酬からの脱却
契約時点で報酬の大半が確定する設計は、成立のみを評価する。成立後に顧客が後悔しようが、生活に無理が生じようが、営業員の評価や報酬が守られる構造では、顧客本位は絵空事となる。
・報酬の可逆性(やり直し)の導入
不適切な販売プロセスや顧客不利益が後に判明した場合、評価や報酬が過去に遡って修正される仕組み、いわゆるクローバックは、時に厳しい制度と受け取られるかもしれない。しかし、これは決して罰則ではない。むしろ、営業員が顧客の真の利益を追求する上で生じる迷いや倫理的な葛藤から、彼らを守る仕組みであり、長期的な信頼関係を守るための支えと捉えるべきである。
・評価の重心を「獲得」から「継続」へ
契約継続率、顧客の理解度、生活環境の変化に応じた見直しへの対応など、顧客との長期的な関係性を評価する仕組みが不可欠である。こうした要素が評価に反映されて初めて、営業の関心は単に契約を成立させることから、顧客と付き合い続けることへとシフトするだろう。評価されるべきは、「顧客の理解が不十分だと判断し、成約を急がなかった」、あるいは、「顧客の状況変化を踏まえ、収益が下がる提案をあえて行った」など、短期的には不利に見えても、長期的には顧客にとって最善の選択をするといった行為だ。
内部告発を阻む「沈黙の空気」
今回の事例において、長期間にわたる不正にもかかわらず、内部告発が表面化しなかったという事実は重い。これは、単に勇気ある人間がいなかったという話では決してない。強い成功体験が続く組織では、「皆がやっている」、「今さら自分が言っても変わらない」、「波風を立てる方が不誠実だ」といった沈黙の空気が醸成されやすい。このような環境では、たとえ心の中で「これは違う」と感じていても、良識ある個人でさえ、孤立を恐れ、自己保身に走り、声を上げることを躊躇してしまう。そして、自ら沈黙という選択を強いられてしまう。
同質的な価値観が濃縮される中で、内向きの相互的な称賛を通じ、不正を不正として認識できない状態が生まれる。「類は友を呼ぶ」という言葉が示す通り、疑問を抱かない者同士が集まれば、異論は排除されていく。
報酬体系は各金融機関の経営の根幹であり、金融庁がその設計を直接的に押し付けるべきではない。成果主義を全面否定することも現実的ではない。
しかし、顧客本位という理念と、実際に評価され、報われている行動とが本当に整合しているのかを問い続ける責任は、当局にあるのではないか。当局の役割は、理念と評価が、同じ方向を向いているかを確かめ続けることだ。その問いかけは、業界にとって時に耳障りかもしれない。しかし、それこそが、金融機関にとって信頼を守るための最も力強いエールとなるはずだ。
「月とウサギ」が示す利他主義
筆者は、「顧客本位」を語るときに仏教説話「月とウサギ」を思い出す。この説話は、飢えた旅人のために、自らの身を火に投じたウサギを通じて利他主義の実践を描く。人は本来、金銭や生存を前にすれば弱い存在であるという現実を前提とした上で、それでも他者を優先できるかを問いかける。
利他主義は、生まれつき備わる特別な徳ではない。それは、日々の迷いや葛藤の中で、それでも他者のために何ができるかを問い続け、少しずつ高みを目指す、人間としての奥深い営みではないか。そして帝釈天が月の中にウサギの姿を残したのは、人々が月を見上げるたびにウサギ(利他の心)を思い出すように、また、その心は簡単に手が届くように見えて、実は到達することが難しいことを示すためにではないか。
完全な利他主義を組織の全職員に求めることは酷かもしれない。しかし、その理想を忘れた瞬間、顧客本位という言葉は空虚な響きとなり、組織は見えない歪みに蝕まれていくのではないか。
組織において、「利他主義」という重たい理想を全職員が共有するには、例えば、以下のような取り組みが考えられる。
・失敗から学ぶ文化の醸成
短期的な成果だけでなく、長期的な顧客価値を追求する過程での試行錯誤を許容し、失敗を責めるのではなく、そこから学び、改善する文化を育む。
・対話と異論を歓迎する風土の構築
組織内の多様な意見や疑問を積極的に吸い上げ、建設的な議論を促す仕組みを作る。上層部への意見具申を奨励し、異論が組織を強くするという認識を共有する。
・長期的な視点での評価制度の確立
上述の報酬の可逆性や評価軸の変更に加え、顧客との長期的な関係構築に貢献した職員を、継続的に評価・表彰する制度を設ける。短期的な数字だけでなく、顧客からの信頼や感謝といった定性的な評価も積極的に取り入れる。
・倫理観の継続的な醸成と教育
倫理研修を単なる形式的なものにせず、具体的な事例を交え、顧客本位の行動とは何かを深く考えさせる機会を定期的に設ける。特に、現場での判断に迷うような状況を想定し、議論を通じて倫理的な判断力を養う。
・経営陣による明確なメッセージと行動
経営陣が率先して顧客本位の理念を体現し、その重要性を繰り返し発信する。口先だけでなく、自らの行動でその姿勢を示し、組織全体の模範となる。
月を見上げるたび、私たちはウサギの姿に利他主義の高みを見る。組織に息づく顧客本位とは、その高みに手を伸ばし続ける、日々の地道な行動の積み重ねに他ならない。それは決して容易な道ではないだろう。しかし、その一歩一歩が、失われた信頼を取り戻し、顧客と共に歩む未来を築く、確かな道となるはずだ。