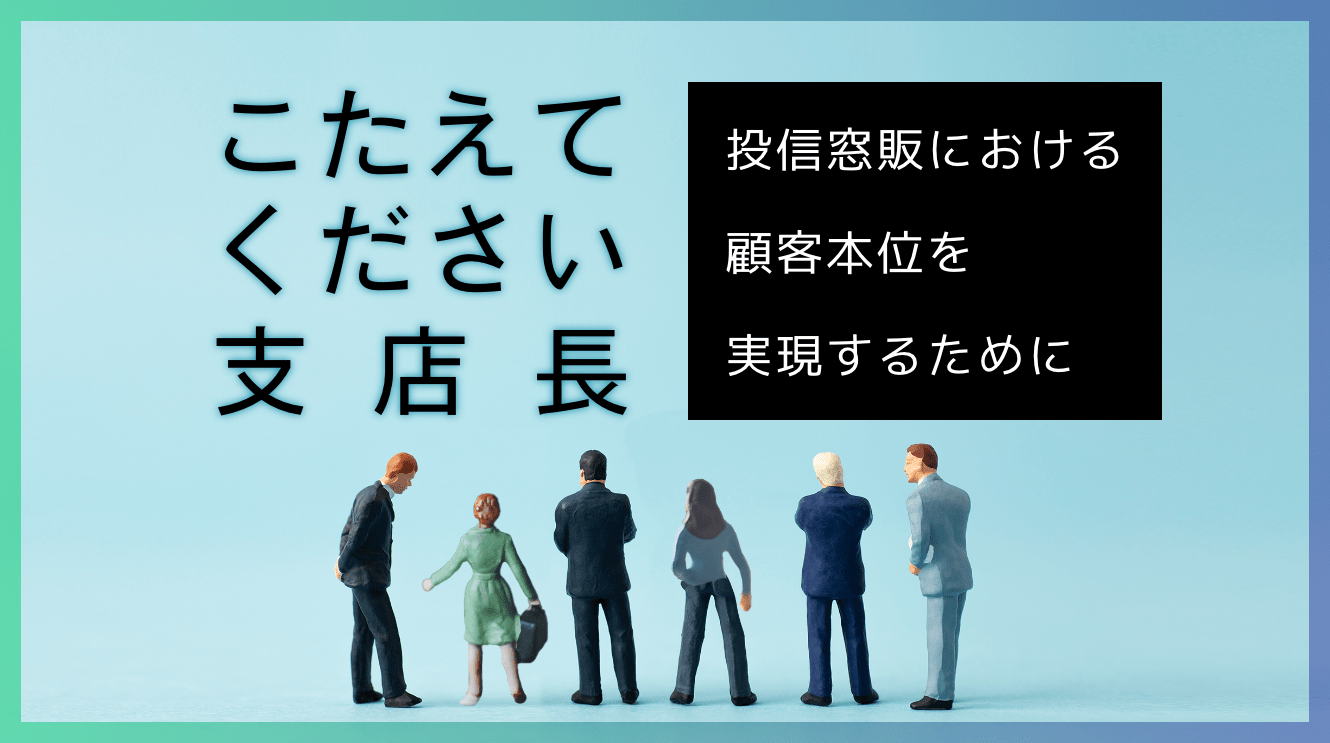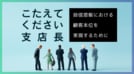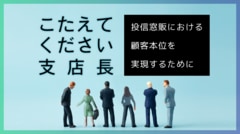Q:職員「ゴールベースアプローチをすれば、お客さま
本位の提案になるということでよいですか?」
A: 支店長「そうですね。当社としての自主KPIにもなっていますから、積極的に取り組んでほしいと思います」
森脇's Answer:
ゴールベースアプローチは手段のひとつであって、これそのものが顧客本位の業務運営の実践を意味するものではありません。この支店長の回答は自金融機関のKPIを達成することに重点を置いた回答であり、顧客本位の活動についての理解がまるでありません。
ゴールベースアプローチは万能ではない
NISAの普及は国民の資産形成にとって望ましいことです。それまで個人で投資を行っていたのは富裕層など、まとまった資金を保有している人が中心でしたが、NISAが開始されて以降、まとまった資金のない一般生活者も投資をするようになりました。自助努力で老後の年金を補完することが主たる目的ですが、このような資産形成としての投資には多くの場合“ゴール”が存在します。それは定年退職です。収入がなくなる定年退職後に取り崩すことを想定し、そのための資金を現役時代に用意しようというわけです。このように明確なゴールを設定できる資産形成としての投資を行う人には、ゴールベースアプローチは有効であると言えるでしょう。
一方、余裕資金の運用としての投資を行う富裕層の場合、その投資活動にゴールを設定することが不適当であることが少なくありません。まとまった資金が常に投資に振り向けられ、相場に応じてリバランスを行ったり、必要があれば現金化して取り崩したり、利回り部分を消費に回したり、その時の状況に合わせるという構えが基本です。さらに次の世代へ相続され、永続的に投資されることも多くあり、そこにゴールはありません。
大まかに言っても、資産形成としての投資と資産運用としての投資とでは目的が異なっており、リスクに対する捉え方も違えば、提案方法やフォローの仕方も当然違ってきます。顧客本位とは、お客さま一人ひとりに合わせて対応するという基本を思い起こしてほしいのです。私たち対面の金融機関が長らくお付き合いしている、そしてこれからも深くサポートしていくのは、ゴールベースアプローチでは必ずしも適切に対応できるわけではない、大口のお客さまも多いのではないでしょうか。
設定したゴールを過信しすぎず、顧客の現状をきちんと把握する
雇用されている労働者の多くに定年退職というものがあるという点で、ある種のゴールはあります。しかし、それ以外においてゴールを決めて投資をするという考え方は要注意です。老後資金という長期の資産形成を除けば、住宅や車の購入、進学、結婚などのお金の工面においては預貯金や融資など投資以外の方法も含めて提案することが望ましいからです。そもそも資金に余裕が多くない一般生活者が、必要資金を運用だけで増やそうと考えるのは避けるべきです。
ゴールベースアプローチが取り上げられる際に、ライフプランも同時に語られることが多いと思います。今後のライフイベントを見越しておき、必要になる資金を計画的に用意しておきましょう、といった言説をよく見聞きします。夢や目標を持つのは良いことです。しかし、人生とは本質的に何が起きるか分からないものであり、そこに細かくプランを立てるということにどれほどの意味があるのでしょう。私たちはコロナ禍を経験しました。それ以前には想像もできなかった事態であり、その渦中では数カ月先の不確実性も実感しました。その後も、世界情勢は目まぐるしく推移し、物価は上昇し、雇用情勢など私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。社会の有り様だけでなく、個々人においても思わぬ転機が訪れるものです。そのような中で、ライフプランを組み立てて、老後にいくら必要、いくらあれば安心という議論はあてになりません。
長年多くのお客さまと接していて思うことは、お客さまの人生は実に色とりどりであり、計画通りにレールの上を進んでいく人のほうが珍しいということ。不確実な将来に不安を覚えるのは自然なことです。そこで必要なことは、ゴールを定めてそこに向かうためのガイドではなく、リスクを想定しながらそれに備え、不安を軽減するためのサポートをすることだと思います。
その上で重要なことは今のお客さまを知ることです。現状を知ることが最優先です。預貯金が少なく、不測の事態に備える資金がない人には円での預貯金を案内しつつ、インフレリスクに対抗するための資産形成としての投資の案内も必要です。お客さまの現状や価値観をよく観察し、今の生活にどれだけ重きを置くのか、将来のためにいくら残すのか確認してください。状況が変われば今の決定も当然変わるのでしっかりフォローしてください。将来のことは常に「分からない」という姿勢で話し合うことが信頼を生みます。不安をあおった金融商品の保有ではなく、常に寄り添う皆さんの存在がお客さまの安心になることを願っています。
支店長は現場に則したルールづくりに貢献を
多くの金融機関において顧客本位の業務運営指針やルールが、一般生活者の資産形成としての投資と、資産に余裕のある人の資産運用としての投資を混同したものになっていることが散見されます。現場はなんとか折り合いをつけながら、時にはお客さまに譲歩していただきながら、ルール内で活動しています。お客さま本位の活動は、お客さまが主役、接する担当者が準主役です。支店長は現状の方針やルールが現場の活動を阻害していないかを点検してみてください。支店長は現場の声を代表できる存在です。ぜひお客さまの現状を吸い上げ、本部へ提言し、お客さま本位の活動をするための基盤づくりに貢献していただきたいと思います。