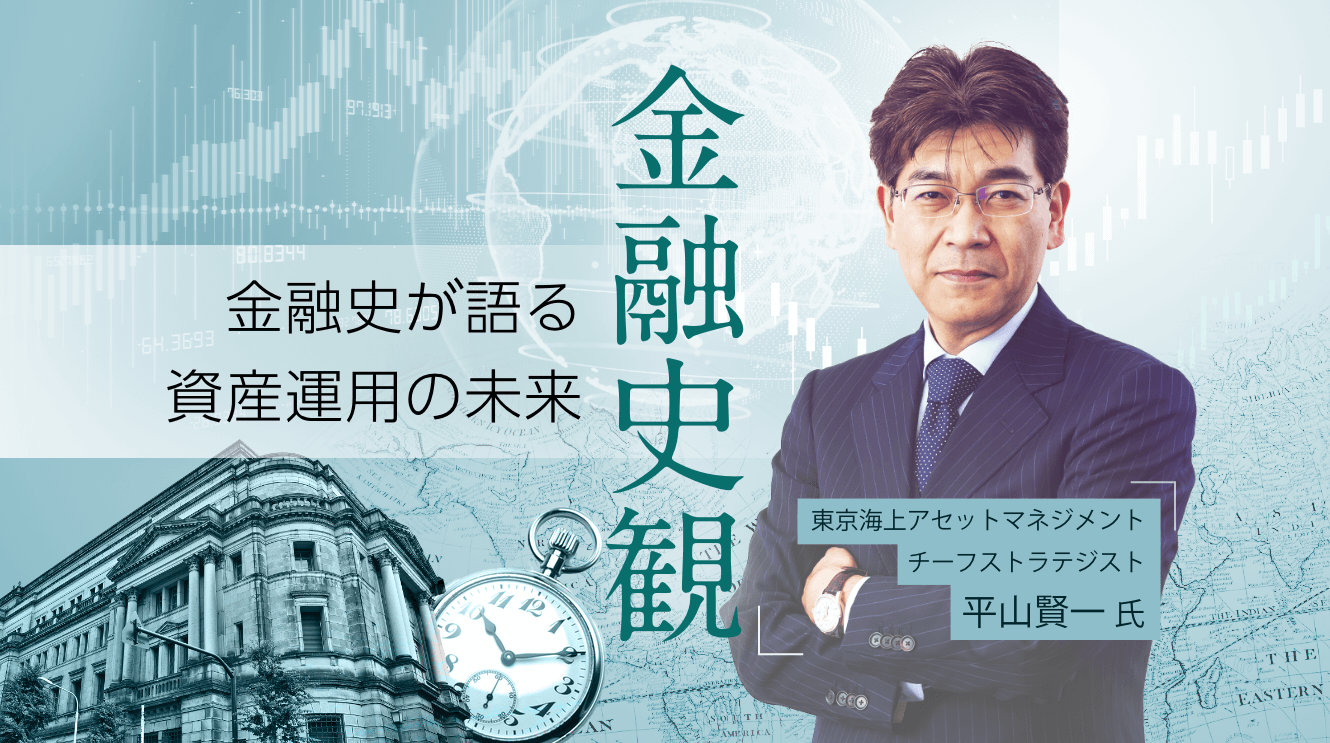資産形成の未来を株式市場および国債市場の歴史から検討してきたが、米国大統領選以降、政治的な要因が資産運用に与える影響が大きくなっている。金融市場は、純粋に経済状況のみが反映されるわけでなく、政治状況も多分に影響するだけに、政治や国家と市場の関係についての注意を怠ってはならない。トランプ米大統領の関税政策が金融市場の変動率を大幅に上昇させていることから、今回と次回の当寄稿では、国家と市場の関係性について整理していきたい。
金融市場は2024年末にかけて、将来の不安を徐々に織り込み始めていたが、大きなショックが走ることはなかった。しかし、2025年4月に米大統領が極端な関税政策を発表したため、金融市場には激震が走った。市場参加者は、急速にグローバルに開かれた経済システムが修正される不安に怯え始めているのである。このような時代において、資産運用をどのように捉えていくのか考えた際に参考になるのが、国家と市場の関係をめぐる歴史観であろう。2008年以降、筆者は、この関係を「振り子の金融史観」と称して議論してきた[1]。
「振り子の金融史観」とは
この史観は、国家と市場の関係が「国家主導の分断(対立)」の時代と「市場主導の統合(協調)」の時代を振り子のように、数十年単位で揺れ動いてきたとするものである。協調の時代は、国境が撤廃され、人的資源、物的資源、および金融資本の流動性が向上し、結果として経済成長が促進される時期を指す。一方、対立の時代は、経済制裁や保護貿易によりグローバル経済の分断が生じ、インフレーションや経済成長の鈍化などの負の側面が顕在化する時期を意味する。この対立と協調の振幅を「振り子」に準(なぞら)えて図1で示すと、右に振れる局面が対立の時代、左に振れる局面を協調の時代となる。
右に振れている局面は、戦争・紛争による世界的な分裂の時期であり、経済成長率は低迷し、金融市場が不安定な状態に追い込まれる。そのため、政府は市場介入を通じて市場の安定を図ろうとする。政府の介入・規制姿勢が強まるため、民間の自由な活動が抑制されるだけでなく、市場参加者は、政府の介入や規制に依存する雰囲気が蔓延する。一方、振り子が左に振れる局面は、平和の進展と共に国境を超えて企業が活動領域を拡張するため、各地の市場が統合されていく時期である。企業は、好景気を享受し、政府の介入が減少し、規制緩和が進むため、自由な経済活動が許容される。
この対立と協調の振幅は、対立が極限まで深化すると協調への逆行が始まり、対立が解消されるにつれて徐々に協調関係が浸透する。そして協調が極大に達すると再び対立へと転じるという「振り子」のような振幅が、数十年ごとに繰り返されてきたのである。
(図1)数十年単位で振幅する「対立」と「協調」の時代
対立と協調が数十年ごとに繰り返されてきた20世紀
過去100年超にわたる振り子の振幅を、具体的に当てはめてみると次のようになる。対立の時代は、①第一次世界大戦が勃発した1910年代、③第二次世界大戦に至る1930年代から40年代にかけて、⑤中東戦争と米ソ冷戦が深刻化した1970年代から1980年代にかけて、そして⑦2017年の米トランプ政権発足以降表面化した米中対立の深刻化や、2021年のBrexit(英国のEU離脱)に加え、2022年のウクライナ紛争に至る2010年代以降などが当てはまる[2]。
一方、この4つの対立の時代に挟まれるように、協調の時代は、国家や地域の枠を越えて統合化が進み、政治的な対立が減少してきた。国家という堅いイメージの壁は消滅し、地球規模での「グローバル」という言葉が多用される時代は、②国際連盟が発足した1920年代、④国際連合が設立された1940年代後半から1960年代にかけて、⑥ベルリンの壁崩壊や冷戦終結を宣言したヤルタ会談の1989年を起点とした1990年代から2000年代が該当する。この⑥の時代は、欧州統合やグローバル化(グローバリゼーション)により世界中の人々が国境を越え自由に行き来し安くなった時代といえよう。
(図2)繰り返す「対立」と「協調」の時代
|
対立の時代①;1910年代(第一次世界大戦) 協調の時代②;1920年代(戦間期) 対立の時代③;1930年代~40年代前半(第二次世界大戦) 協調の時代④;1940年代後半~60年代(戦後復興期から経済成長期) 対立の時代⑤;1970年代~80年代(第四次中東戦争、米ソ冷戦) 協調の時代⑥;1990年代~2000年代(グローバリゼーション) 対立の時代⑦;2010年代以降(ウクライナへのロシア侵攻、米中対立) |
右に向かっていた振り子が極まると、左への振幅をはじめ、左端に行き過ぎると右旋回が始まることになる。たとえば、図2のように、対立の時代①が極まり第一次世界大戦が終戦を迎えると協調の時代②が始まるが、自由な経済活動の帰結として行き過ぎたバブルが生じ、左端に振り子が行き過ぎる。
その反動としてバブル崩壊と経済減速が生じると、限られた資源の分捕り合戦が始まり、対立の時代③が始まる。金融市場は不安定になるため、政府は国債市場の安定を図るために国債オペによる、長期金利の釘付け政策などを実施し、市場の不安心理を抑え込もうとするわけである。さらに、市場の力よりも国家の力が強調される時代には、物価上昇を力ずくで抑え込み(公定価格の強制)、外国為替レートの変動も政治的に操作される。そのため、外国為替市場の歪みが大きくなり、既存の国際通貨システムが立ち行かなくなり、振り子の右端では国際通貨システムの転換が生じやすくなる。たとえば、①には金本位制が停止され、③には新たにブレトンウッズ体制への転換が図られている。
第二次世界大戦後は協調の時代④が始まり、戦後復興による経済成長を謳歌するものの、その行き過ぎは、米国株式市場の場合にはニフティ・フィフティ相場を形成した。しかし、その後はインフレ率が高いにもかかわらず株価が横這う実質株価下落時代を迎えることになった。この時代は対立の時代⑤でもあり、中東での戦火や米ソの冷戦が、国際社会の分断を加速したのである。この対立の時代には、ニクソンショックやプラザ合意など国際通貨システムをめぐる揺らぎが頻発したのは記憶に新しいところであろう。この不安定な時代を越え、1990年代以降は、グローバリゼーションの掛け声の下、世界中の壁が取り払われ、自由な経済活動が進展する協調の時代⑥を経験する。この時代には、90年代末のITバブルや2000年代のサブプライムバブルなどを経験し、振り子が左端に行き過ぎていたことが理解されよう。
21世紀の新しい現実
以上のように、20世紀の振幅は、右に向かう国家対立の振り子と、左に向かう市場主軸の協調の振り子が、概ね交互に繰り返されてきたと言えそうである。果たして、21世紀もこのパターンは繰り返されるのであろうか?
具体的に見てみると、2020年代にかけては、米中対立だけでなく、ロシアによるウクライナ侵攻、中東での政情不安が台頭しており、対立の時代⑦が進捗している途上と言えよう。ロシアや中国政府による金地金購入や、暗号資産の台頭など、ニクソンショック以降の国際通貨システムについての揺らぎもあり、20世紀と同様に右向きに振り子の時代に通貨の仕組みに対する揺らぎが生じている。また、グローバル金融危機以降は、不安定な金融市場を落ち着かせるために、各地域の中央銀行は積極的に非伝統的金融緩和政策により、市場の混乱が発生するのを防いできた。しかし、コロナ禍後のインフレ率の上昇が、積極的に中央銀行が緩和政策を実施する余地を狭めている。さらに、トランプ大統領による関税政策は、物価の底上げ観測を台頭させているため、金融市場を安定化させる金融政策を発動しがたくなっているのが新しい現実と言えよう。
それだけに、不安定な金融市場を落ち着かせる手立てが限られ、国家と市場の蜜月時代は終焉を迎えつつあるわけである。以上のように考えると、振り子が右に振れている現代は、株式市場を含む金融市場の変動率が上昇し、資産運用にあたっては、胃の痛い時期が本格化することは避けられないのかもしれない。それでは、この動きの先には何が待ち構えているのだろうか?われわれが、個人投資家に対してどのようなアドバイスをしていったらよいのか。その点については、次回(第12回)の最終回に記すことにしたい。