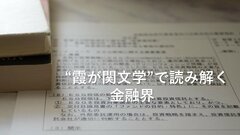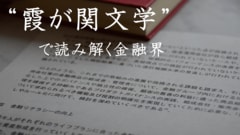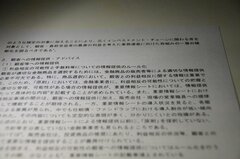本連載ではこれまで、金融庁の行政運営の基盤となっている二つの対照的な考え方である「プリンシプルベース」と「ルールベース」の関係性、あるいはせめぎ合いという視点から、さまざまな資料を読み解いてきました。ただ、当局ウォッチをしばらく継続している筆者の率直な実感として、この単純な二項対立によって金融庁の政策を分析することは、もはや時代遅れになってきているようにも思えます。
そこで今回は、既存のプリンシプルの枠組みに依存することなく、金融庁が金融機関に対応を促す場面で使用されるプリンシプルのようなもの、いわば「ステルス・プリンシプル」の多様化・高度化という観点から、新レポート(「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2025」)の内容を分析してみます。
新レポートは、主要な論点として、資産運用業全体の高度化、確定拠出年金(企業型DC、iDeCo)サービスの高度化、確定給付企業年金(DB)サービスの高度化の3つの柱を掲げています。投資信託のコスト体系の透明化、私的年金分野の運用力向上など、旧レポートの延長上にある論点が多数を占める中、今までにない新機軸的な論点もいくつか打ち出しています。そのうちの一つが、国内投資の促進です。
国内投資促進といっても、こちらの解説記事でも触れように、新レポートの中で直接的に「国内スタートアップに促進せよ」と明記しているわけではなく、金融機関側の「主体的」な対応の期待感をにじませるにとどまっています。たとえば、旧レポートがオルタナティブ投資全般の動向をザックリと概説するにとどまっていたのに対し、新レポートではわざわざ国内オルタナティブ投資に独立した章を設け、その伸びしろの大きさを強調しています。
日系大手におけるオルタナティブ投資全体が拡大基調にあるものの、国内向けは横ばいであるというデータを提示し、「グループ会社の知見を活用しやすい環境にある」と指摘している箇所からも、国内の非上場株式への投資を強化するよう、日系大手各社に暗に発破をかける狙いが読み取れます。金融庁幹部はレポート公表に合わせ、報道陣に対し「国内の成長を促進する観点からは、日本のVCに対する投資が進んでほしい」と述べ、期待を隠してはいません。
これまで金融庁がルールに依存せず事業者に何らかの行動を促す際は、たいてい、何らかのプリンシプルを持ち出してきました。リテール分野のリスク性商品についてはFD原則が、機関投資家についてはスチュワードシップコードやアセットオーナープリンシプルといった各種プリンシプルが、罰則規定などを用いることなく、事業者を当局の意図する方向へ誘導する役割を果たしてきたのです。
ところが新レポートを見ると、少なくとも国内オルタナティブ投資の章立てに、プリンシプルについての直接的な言及はありません。また、プリンシプルとルールの両方にまたがるキーワードとして最近、ことあるごとに当局が多用している「最善利益」という言葉すら見当たりません。それでも、先ほど紹介した幹部の発言にみられるように、新レポートの背景には国内投資拡大への期待感がたしかに存在するのです。
ステルス化はサステナブルの分野でも
ルールの範囲外にある事柄を推進しながら、プリンシプルへの言及を避ける手法を、ここで仮に「ステルス・プリンシプル」と呼ぶことにしましょう。特定のプリンシプルの力を借りることなく、そのつど調査データなどをもとに課題認識を示し、対応を促すといったステルス・プリンシプルの手法は最近、国内オルタナティブ投資以外の文脈でも利用されるようになりました。
その典型的な一例が、サステナブルファイナンスです。金融庁はESG投資の機運の高まりを受けて「サステナブルファイナンス推進室」を設け、基本的にはESG投資を推進する立場にあります(これまでテーマ型投資を批判してきた整合性を取るため、当局はこれまで理論武装にかなり心血を注いできました。ただ、これまでの記事でも取り上げたように、ESG投資が「テーマ型」であるかどうかについては過去の当局内には一時多少の混乱がみられました)。
過去の情報発信を見返すと、サステナブルファイナンスを推進する上で、FD原則などプリンシプルに言及する記載は見受けられません。ESG投資のグリーンウォッシュを防ぐ文脈では各種資料にFD原則への言及がみられますが、これは牽制の意味合いが強く、推進とは別の趣旨と考えられます。
6月に金融庁が開いた行政事業レビュー(旧事業仕分け)では、金融庁が「サステナブルファイナンス有識者会議」や官民コンソーシアムなどに議論を「丸投げ」することで、サステナブルファイナンスを推進する主体が曖昧化しているとの指摘が飛びました。当局内にサステナブルファイナンスを「推進」する組織を設けながらも、具体的な議論については半官半民的な位置づけの会議体や組織に委ね、政策的・理論的な妥当性に関する責任を当局が丸かぶりしないよう、巧妙に環境整備を仕立てているというわけです。
このように民間の事業者や専門家をまじえた枠組みを噛ませることも、ルールにもプリンシプルにも依拠することなく事業者にメッセージを発信するステルス・プリンシプル的な手法の一形態といえるでしょう。
象徴主義化する"霞が関文学"
……と、ここまで読んで頂いた方は、なんだか神学論争っぽいというか、重箱の隅をつつくような話に陥っているように感じられるかもしれません。
たしかに、FD原則のような既存のプリンシプルの機能が一部、ステルス・プリンシプルに移行しただけと考えれば、行政運営を進める上での全体のバランス感にはさほど影響がないようにも思えます。
しかし筆者は、ステルス・プリンシプルを当局が多用するようになれば大きな問題が生じると考えています。というのも、不文律の領域が拡大することで、官民間がコミュニケーション不全にはまる懸念があるからです。
プリンシプルはある意味で、霞が関文学が過度に難解化し、本来伝えるべきメッセージが事業者に届かなかったり、当局が意図しないような曲解が拡散したりといったことを防ぐ役割を担っていると考えられます。「金融庁が何をさせたいのかはよく分からないけど、少なくとも『原則』と矛盾することや、全く無関係なことを強制されることはないだろう」と、事業者側が当局の出方をある程度予測できるからです。
ちなみに本連載は、霞が関文学の行間に込められたメッセージを読み解くという趣旨で不定期配信を続けています。その上で、根拠の薄弱な陰謀論めいた過剰解釈に陥ることのないよう、資料を読み込む上では金融庁の「中の人」への取材を試み、行き過ぎた独自解釈を可能な限り避けるよう心がけています。
従来の明文化されたプリンシプルから、当局がステルス・プリンシプルに重心を移行させていくとすれば、担当官たちの意図を取材し、報道する立場の責任と役割はいっそう大きくなるはずです……が、本当にそれでよいのかという論点もあるでしょう。公表される1次資料だけを読んでも当局のメッセージを十分に汲み取ることがもはや不可能だとすればすれば、それはそれで健全な状態とは言えないように思えます。「霞が関文学というものは可能な限り難解で、余白が大きく、かつ多義的であるほど美しい」といった、象徴主義的とも取れる極端な美学が庁内で蔓延すれば、官民間のコミュニケーションはいっそう複雑化し、いずれ予期せぬ擦れ違いにつながってしまう危険があるのではないでしょうか。