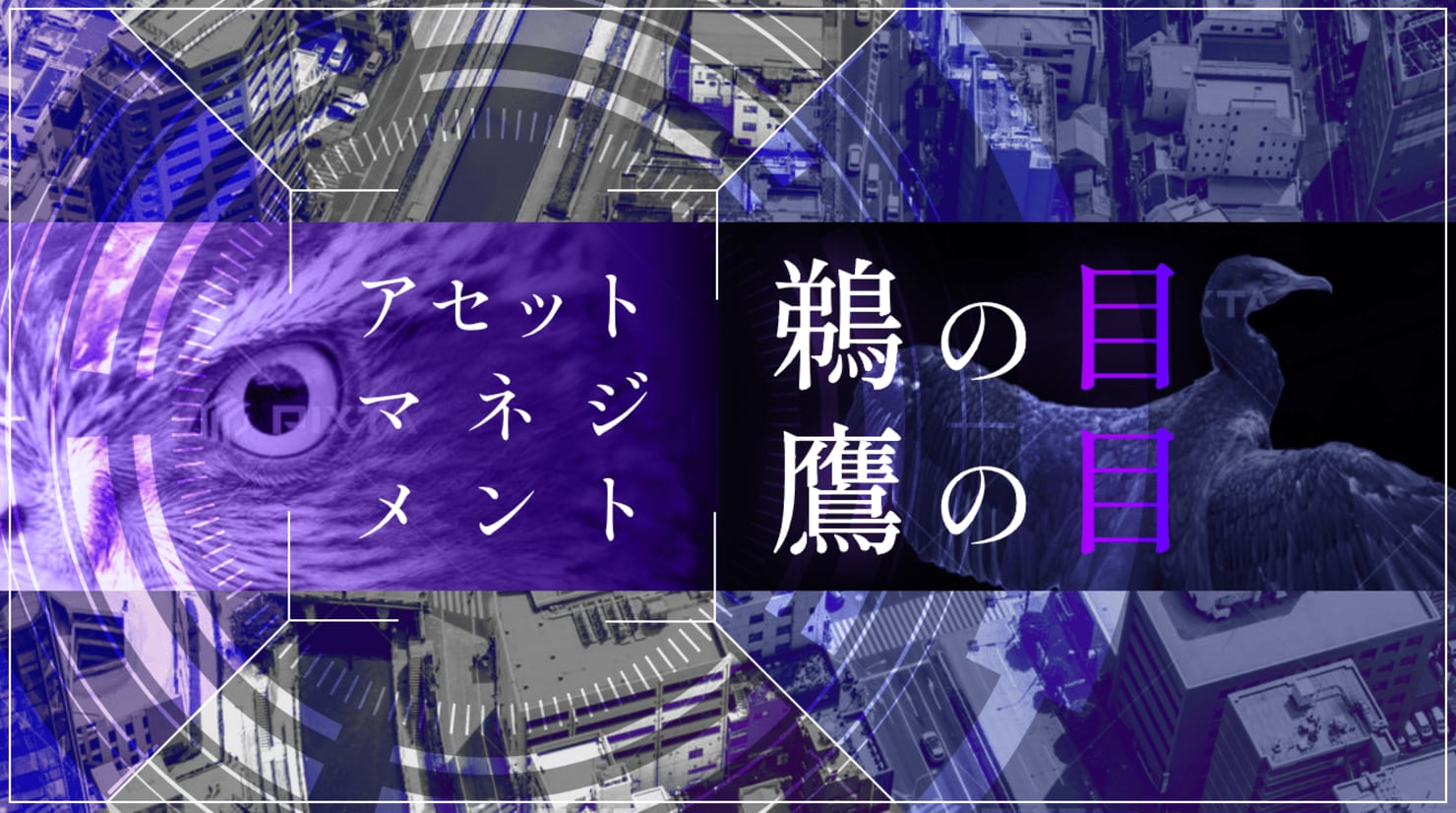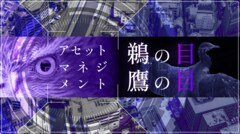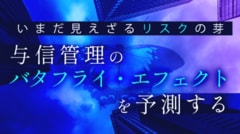4.今後に備えて反省すべき点は?
幸いにして、筆者の秘策はソコソコ上手く行った。ただし、100点満点とはいかない。改善を検討する余地はそこかしこにある。
そこで、反省すべき点や今後課題とすべき点をいくつ挙げた上で、個々に検討してみる。
・株式を米国株式投信に変える必要はないのか
・債券に関する考え方を見直す必要はないのか
・債券の持ち方は現状のままでよいのか?
・通貨ヘッジのあり方を再考する必要はないか?
・そもそも筆者の秘策で想定する利回りが稼げるのか?
株式を米国株式投信に変える必要はないのか
前述の通り、投資家に対する利益の還元という点では米国株式の方が優れている。しばしば株主資本主義と揶揄されることもあるくらいだ。
それを知りながら、筆者が全世界株式にこだわったのは、先進国を上回る新興国株式の成長力・爆発力に期待したからだ。
ただし、今、改めて過去データを見ると、この考え方は揺らぎつつある。過去30年間、全世界株式が米国株式を上回る時期はほとんどないように見えるからだ[1]。もっともその原因が新興国株式とは限らない。予断を持たず、改めて調査を行い、その上で対応を考えたい。
債券に関する考え方を見直す必要はないのか
筆者は、「年齢が上がるにつれ債券比率を増やすべき」という業界ロジックにはかねて否定的であったし、今も少なからず批判的だ。株式ではなく債券を選択することでリターン低下は不可避だし[2]、シニアな投資家が惑わされ、適合性の低い高リスク債券に誘導されることを恐れるからだ。
ただし、今回経験してみて、投資対象となる債券を適切に選択すれば、株式投資によるマイナスを軽減する効果が高いことを実感した。
したがって、今の筆者の考え方は、“株式でリターン追求を目指すシニアな投資家は、債券も併せ持った方がよい。ただし、格付けが高く、金利以外のリスクは排除した満期の長い先進国国債を選ぶべし”、ということになる
債券の持ち方は現状維持のままでよいのか?
上記の通り、超長期米国債ETFへの投資により、一定の成果を得られた。しかしながら、今は、その後も定額積立の1/3を機械的に投じることでよいのか疑問を持ち始めている。
同ETF投資の成果があったのは利回りが低下したからだ。そこに新規資金を投じるのは低い利回りに甘んじ、かつ将来の利回り上昇局面でキャピタルロスを食らうことだ。これでよいのか。
もちろん、筆者は、この点を全く考えていない訳ではない。米国10年国債利回り(超長期国債利回りの代理変数である)を基準に、これが3%を切ったら、超長期米国債ETFを控え、5%超では増額するつもりでいる。ただし、現状の3%台は、米国の実態からして低過ぎる可能性がある[3]。であれば、現時点で、超長期米国債ETFへの投資を抑制すべきではないか。
残念ながらこれも即座に結論が出せるテーマではない。上記の方針をボトムラインに、運用を継続していき、その過程で、今後より適切な解決策を見出していく所存である。
なお、米ハイイールド社債ETFに関しては、株式急落時の下値抑制効果は得られたので、現状通り今後も投資を継続する方針でいることは申し添えておく。
通貨ヘッジのあり方を再考する必要はないか?
債券ETFに留まらず、株式投信についても、今回の通貨変動の大きさを踏まえ、全てを通貨リスクに晒すのではなく、一部ヘッジを考え始めている。ただし、ヘッジ付の全世界株式投信は存在しない(米国株にはある)。先述の米国株式シフト要否検討と併せ考えたい。
そもそも筆者の秘策で想定する利回りが稼げるのか?
これも答えに窮する質問である。筆者にとって新NISA参入の秘策は、一種の実験であって、是が非でも稼がないといけない目標がある訳ではない(といってもマイナスは困るが)。
強いて言えば、全世界株式で株式並のリターンを、ハイイールドETFでその半分のリターンを、超長期米国債ETFはリターンゼロ(株式下落を減殺する役割以外は期待しない)と置くと、株式投資の半分程度のリターンを狙っている、という計算になろうか。
ただし、筆者は、これを下限とし、さらに上値を目指すつもりでいる。現時点では、明確なアイデアがある訳ではないが、先述の債券の持ち方を工夫するだけではなく、市場環境に応じて、定額積立に傾斜をつけるといった手立てを講じていくつもりだが、これも今後の話だ。
5.まとめ
以上、見てきた通り、今回の市場の乱高下は、筆者の秘策が相応に効果を発することが確認できたとともに、今後の課題も明らかとなった。
単なる自慢話ではなく、読者諸賢にとって役に立つような見解を盛り込んだつもりだ。とりわけシニアな投資家で、新NISAにこれから新規参入しようかどうか迷っている方々に対しては、太字記載の部分が役に立つのではないか。とすれば筆者として望外の喜びである。
[1] 全世界株式の6割以上を米国株式が占めていることに鑑み、両者の指数(円ベース)でのリターンを比較してみた。1995/04~2024/07までの期間で、両者の相関は、0.97だが、累積パフォーマンスは米国株の方が4%近く上回っている。より細かく見るために、36か月の移動平均で両者を比較してみたが、全世界株式が上回っているのは,2007年から2012年までの5年間のみ。ただし、これが新興国に起因するのか、その他先進国(特に日本)に原因があるのか、さらに精査を要する
[2] ある学者というか、YouTuberは、資産運用には物価連動国債(日本版インフレ連動債)が最適と主張している。インフレによる資産の目減りを防ぐ効果があるというのがその根拠だ。筆者もその考え方には同意する、ただし、自らの一生/老後を賄えるだけの資産形成が完了できていれば、の話だ。多くの投資家は、それをクリアすべく、四苦八苦している状況にあり、これを踏まえた主張とは考え難い。機会があれば、当該YouTuberに訊いてみたいものだ
[3] 経済学が教えるところに従えば、名目長期金利は、期待インフレ率と実質経済成長率との足し算で粗い推計が可能とされる(フィッシャー公式)。米国の期待インフレ率をFRBの目標に基づき2%とし、過去実績を参考にその実質経済成長率を2%と仮置きすると合計で4%。すなわち、米国長期金利は名目で4%目処ということになる。もっとも実質経済成長率の事前予測は困難とされていることを考えると、この目途が正しいか否かは後にならないとわからない