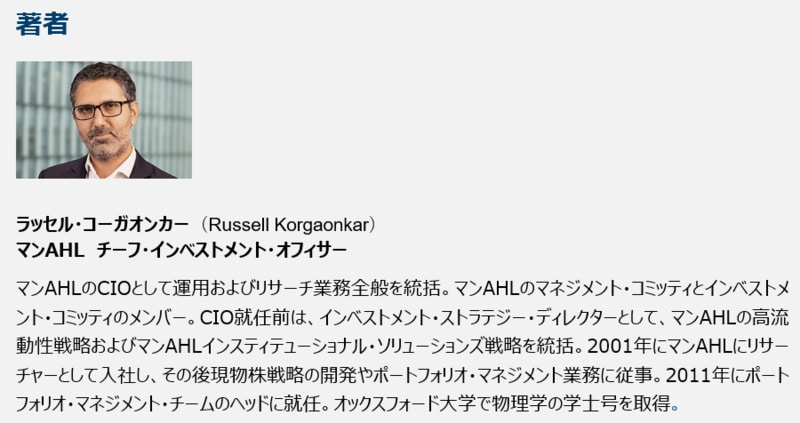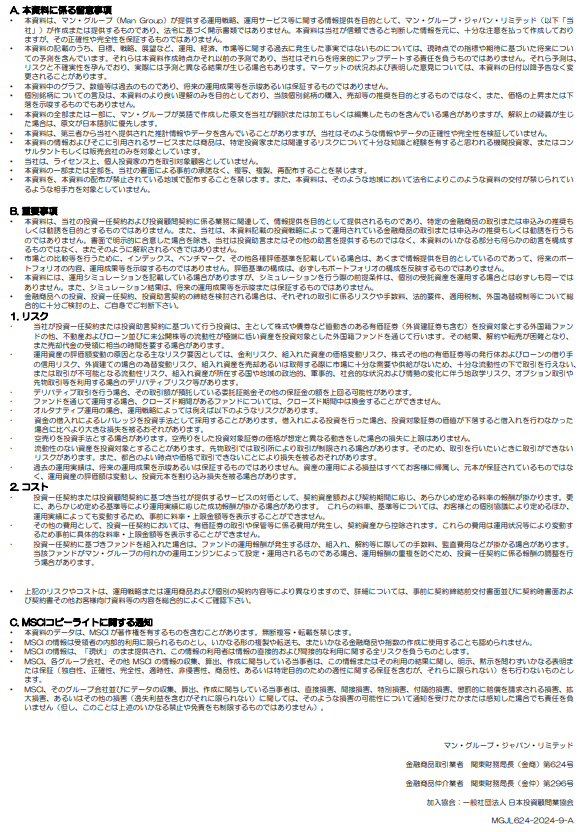はじめに
本レポートでは、マンAHL※のチーフ・インベストメント・オフィサーであるラッセル・コーガオンカ―が定量運用においてどのように通貨や先物といった比較的容易にアクセスできる金融商品の取引から、オルタナティブ市場等のニッチで複雑な市場での取引を開拓してきたかについて掘り下げてみたいと思います。
※マンAHLは、英国ロンドンに本拠を構え、様々な戦略を提供するマン・グループ傘下の運用会社です。コンピューターを駆使したクオンツ運用(定量分析運用)を1987年から35年以上行っている研究者集団で、その世界のパイオニアとして知られています。
出発点
マンAHLは1987年に定量運用を開始しました。当時はリサーチ・チームの大半が学術研究のバックグラウンドを持っていた一方で、トレーディング経験は一般的な金融商品に偏っていました。そのため先物や通貨だけでなく、オルタナティブ市場にも進出するためには、店頭(OTC)商品に関する深い知識と運用経験を有する人材を採用し、チームを多様化させる必要があると考えました。このような考え方は、リサーチやトレーディング・チームだけでなく、法務からコンプライアンス、バックオフィスまで、広範囲の業務にわたって適用されました。
より複雑な市場への入り口
「基本を正せば、結果は後からついてくる」はよく知られた格言ですが、オルタナティブ市場等を取引する際にも当てはまります。取引所商品を定量的に取引するための堅固な基礎を築き、インフラを整えなければ、より複雑な市場を開拓することは極めて難しいといえます。
オルタナティブ市場等(その多くはOTCで取引されています)に注目し始めた当初、われわれはこれらの市場はコア市場を補完する小規模の市場であろうと予想していました。しかしながら、それは大きな間違いでした。当初の予想よりも多くの市場が存在することが判明しました。また、市場へのアクセスが容易ではないからといって、必ずしも流動性が低い訳ではないことも明らかになりました。
とはいうものの、市場によってはその複雑性を理解するのに数ヶ月、あるいは数年かかることもあります。前述のように、先物市場以外の市場に進出するためには、運用以外の業務分野においても堅固な体制の確立が必要となります。プライシング、データの入手可能性、データの正確性などは、われわれが長期にわたり直面してきた課題の一例です。しかしながらこのような参入障壁は、ひとたび克服すれば、報われる可能性があります。
オルタナティブ市場の魅力とは
オルタナティブ市場の魅力は何といってもこれらの市場の多くが、投資家にポートフォリオの拡張機会を提供し、伝統市場のリスクを補完するなど、差別化されたアルファへのアクセス機会を提供することにあります。より広範囲の市場を取引することで、投資家のポートフォリオの質と頑健性が高まり、パフォーマンス向上につながります。さらに、より多くの市場を取引することで、運用戦略全体のキャパシティが拡大する可能性があります。
常に見直しを行う
われわれは2005年にクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の定量的取引を開始しました。その後も債券、金利スワップ、現物株、ボラティリティ取引(価格がどれだけ上昇/下落するかで収益獲得を目指す取引)、To-Be-Announced取引(TBA取引。米国住宅ローン担保証券の先渡契約)、中国市場、キャタストロフィー・ボンド(CATボンド)、仮想通貨などのリサーチも行い、運用戦略に組み入れてきました。
これらの市場のリサーチでは、思考の転換が必要となったことがたびたびありました。市場が当初考えていたよりも奥が深いことを認識したり、特定の商品の取引アプローチを変更することなどもありました。2004 年にその分散効果に期待し、CAT ボンドに注目し始めた当初は、トレンドから収益獲得が可能ではないかと考えていました。しかしながら、リサーチを進めるにつれて、取引パターンが断続的であることと、ビッド/オファーのスプレッドが広いことなどからトレンドフォロー戦略には適さない市場であることが分かってきました。
定量運用マネジャーとして、われわれはシグナル(資産価格が上昇/下落しそうかを示すインジケーター)を探しますが、最終的に自然災害を予測することは不可能であるとの結論に至りました。当時の一般的な見方は、CATボンドのような債券の定量運用は不可能であるというものだったものの、われわれはそうではないことを認識していたため、粘り強くリサーチに取り組みました。最終的にわれわれが開発した CAT ボンドの取引方法は、より有利なプライシングを確保するために、よりパッシブなアプローチを採用するというものでした。このことは当初われわれが想定していたものではなく、未知の領域に足を踏み入れる際には、考え方に柔軟性を持つことの重要性を示すものとなりました。余談になりますが、CATボンドの場合、大規模言語モデル(LLM)が、目論見書から重要な情報を抽出するのに有用であり、ビジネスの拡張性を高めることが分かりました(この点の詳細は、「マン・グループの洞察シリーズ②資産運用における生成AIの活用方法」の「その2: キャット・ボンド取引のための情報抽出」をご参照下さい)。
仮想通貨取引
仮想通貨は、資産クラスとしての成熟度が高まるに従って、近年では投資対象としてメインストリームになりつつあります。私は、休暇から帰ってきたリサーチ・チームの一人が、サトシ・ナカモトによる仮想通貨の論文を読んで、取引の可能性を熱く語っていたことをはっきりと覚えています。当時、仮想通貨のAML(マネー・ローンダリング防止対策)とKYC(本人確認手続き)プロセスはあまり整備されておらず、仮想通貨の取引所は機関投資家に必要な堅牢性が不足していました。そのため、われわれは仮想通貨の取引を保留しました。しかしながら仮想通貨は他の資産クラスと低相関であることや、分散されたポートフォリオの一部として保有することのメリットを考慮し、2020年に再度機関投資家が取引するにふさわしい資産クラスかどうかを再検討しました。現在ではボラティリティが高いことを考慮し、リスク管理に重点を置きながら、仮想通貨へ投資を行っています。
行き詰まりは当然のこと
ここまでは、長年にわたるわれわれの調査研究が実を結んだケースについて言及してきましたが、全てがそうであった訳ではありません。結果が出なかった調査研究も多数あります。
一例を挙げれば、われわれは数年前にアルミニウムの現物取引機会を調査しました。アルミニウムは、ポジティブキャリー(保有/調達コストよりも高い利回りやリターンを提供し、長期的に保有することで収益を生む)を提供する数少ない金属です。われわれは、損益がどの程度になるか、また、われわれの運用戦略にとってプラスになるかどうかを見極めるために、数千トンのNASAAC(北米特殊アルミ合金契約)を購入し、米国の倉庫に保管して販売しました。しかしながら、この過程で税金面でのマイナス点が明らかになったことから、これ以上調査を急ぐ必要はないと判断しました。
このように、リサーチでき詰まることがあるものの、われわれがチームで共有しているメッセージは「探求を続ける」ことです。そうすることで、資産運用とポートフォリオ・マネジメントの最前線に立ち続け、投資家に優れた投資機会をもたらすことが可能になると考えています。
次なるフロンティア
われわれはよく取引する新たな市場がもうないのではないかと尋ねられます。実際には、投資対象市場の数は増え続けており、より複雑なものとなっています。10年前には仮想通貨を流動性が高い取引所で取引できることは考えられませんでしたが、現在では可能になっています。われわれは仮想通貨だけでなく、バッテリー・メタルなどの新しいコモディティや気候変動関連取引などにも注目しています。
また証券化クレジットにも投資機会があると考えています。数兆ドル規模の大きな市場であるものの、複雑な構造を理解するためには専門知識が必要で、参入障壁が高いことから、これまでは定性判断に基づく投資判断が中心となっています。われわれは2013年にモーゲージ・パススルー取引を開始したものの、調査を続けた結果、先物取引以外の投資機会のほんの一部しか捉えていないことが明らかになりました。このような金融商品を大規模に取引できるようになれば投資妙味は大きいと考えています。
まとめ
われわれはパイオニア精神を維持することで、リサーチと新規市場の開拓の最前線に立ち続けており、今日では400以上の非伝統市場で取引を行っています。新しい市場はそれぞれが固有の課題を提示するため、われわれは常に適応、革新、見直しを迫られますが、その結果投資家のポートフォリオにおいてより有益な投資機会となる可能性があります。われわれは、市場が進化し続ける中、次にどのような投資機会を発見できるか期待しながらリサーチを行っています。