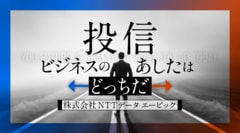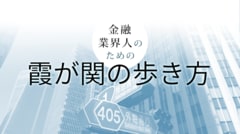|
3人のプロフィール A氏:最近企業年金基金に常務理事兼運用執行理事として着任、本体では経理・財務関係の仕事に長年従事してきた。 B氏:常務理事兼運用執行理事として8年の経験があるベテラン。プライベートアセット投資には積極的。 C氏:B氏同様運用経験の長いベテラン常務理事兼運用執行理事。最近プライベートアセット投資にはやや慎重姿勢。 |
改めて考えるPA投資の意義
A氏 これまでのBさん、Cさんとの議論を通じてPA投資の概要やリスクの所在が理解できるようになりました。2022年度のように株式も債券も全て駄目、オルタナ投資であるマルチアセットやヘッジファンドも低迷するような状況では、安定したリターンを獲得していくために、PA投資への取り組みが必要と改めて認識した次第です。
B氏 2023年度は株式が高騰しポートフォリオ全体のパフォーマンスも平均的なDBで8%台のリターンになったと思いますが、今後も株式が好調を持続する保証はなく、Aさんご指摘のように2022年度を振り返って考えると、伝統4資産主体のポートフォリオでは継続的に安定したリターンを実現するのが難しくなってきており、他の多くのDBでもPA投資の割合を増やしたい、新たにPA投資を始めたいという声は多いようですね。ただ、PA投資ならなんでもよいのかということでもなく、米国の不動産やベンチャーキャピタル(以下VC)は長引く高金利の影響で今は様子見というところでしょうか。
C氏 確かに、資産運用の世界では極めて居心地の良い、低インフレ/低金利/グローバリゼーションによるグレート・モデレーション(大いなる安定)は、途中リーマンショック期に中断することもありましたが、これまで数十年近く続いてきました。しかし、新型コロナショックやロシアによるウクライナ侵攻を契機とした高インフレ、高金利、グローバル経済のデカップリングの進展等により転機を迎え、ニューノーマル(新しい常態)を模索する時代に入ったように思えます。短期的には不確実性が高まっていると思いますが、年金は長期運用が基本ですし、なかでもPA投資は長期的な視点で投資して流動性プレミアムという一種のスプレッドを獲得するものなので、目先の不確実性にとらわれず、粛々と投資を継続するということが大事だと思います。確かに、VCや海外不動産は価格面で調整局面が続いているので、初めてPA投資をする方には難しい局面だとは思いますが、インフラやPDは当面安定したインカム収益が期待できるので、このあたりからスタートすればよいのではないでしょうか。PA投資を始めたのはよいけれど、2~3年赤字が続くと資産運用委員会での説明も苦しくなりますよね。
B氏 ご指摘の通りですが、VCを含むPEはビンテージ(ファンド組成年)の分散が非常に重要ですので、既に投資をされている場合は、景気後退による調整局面でも、継続的に投資をしていくことが肝要でしょう。一般的にはバリュエーションが下がっていれば、将来大きなアルファで高いパフォーマンスを示すケースが多いので、買いのチャンスという見方もできます。
A氏 資産運用でもう1つ困ったことは、高止まりするヘッジコストです。多くのDBはインカム系のPA投資(インフラ、不動産、PD)では為替ヘッジをするのが一般的です。あるコンサルタント会社の調査ではおよそ8割程度はヘッジをかけているようです。ドル円の短期金利差からくるヘッジコストは6%近い水準になっており、インフラでもコアのオープンエンド型ファンドがドルベースで年間8%近いトータルリターンを計上しても、円ヘッジ後のリターンは2%程度になってしまいます。その点、PDは変動金利主体の貸付金なのでドル円のヘッジコスト上昇は貸付金のベースレート(SOFR)の上昇で吸収可能であり、円ヘッジを前提とする投資家にはありがたいです。
C氏 FRBも年内には利下げを始めるみたいですし、いつまでも6%近いヘッジコストが続くということではないでしょうから、長期的な視点で考えて今は我慢の時でしょうね。
B氏 株式と債券の相関が本来あるべき「負の相関関係」に戻らないのではという懸念もあります。株式と債券の負の相関は伝統4資産主体の資産運用における分散投資、リスク抑制の基本です。2022年のようにFRBの急速な利上げを起点とした債券安(金利上昇)、それに伴う景気後退を懸念した株安やクレジットスプレッドのワイドニングで、主要資産は全部安で逃げ場のない状況となり本当に困りました。
C氏 歴史的に見てもFRBが急速な利上げをする局面では、株式と債券の相関は逆転し「正の相関関係」になっています。今後、インフレや労働環境が落ち着いてきてFRBが利下げを開始する局面になれば、長期的に見ればですが、本来の「負の相関関係」に回帰していくのではないでしょうか。
とはいっても、利下げ局面の後には利上げ局面が再来するということであり、時折発生するかもしれない株式と債券の相関関係の逆転を考えると、伝統4資産とは相関が低く、安定したインカム収益が期待できるPA投資の位置付けはさらに重要になってくるのだと思います。
A氏 なるほどですね。少し難易度が高い話でしたが資産運用委員会でPA投資を審議するときの説明に使わせてもらいます。