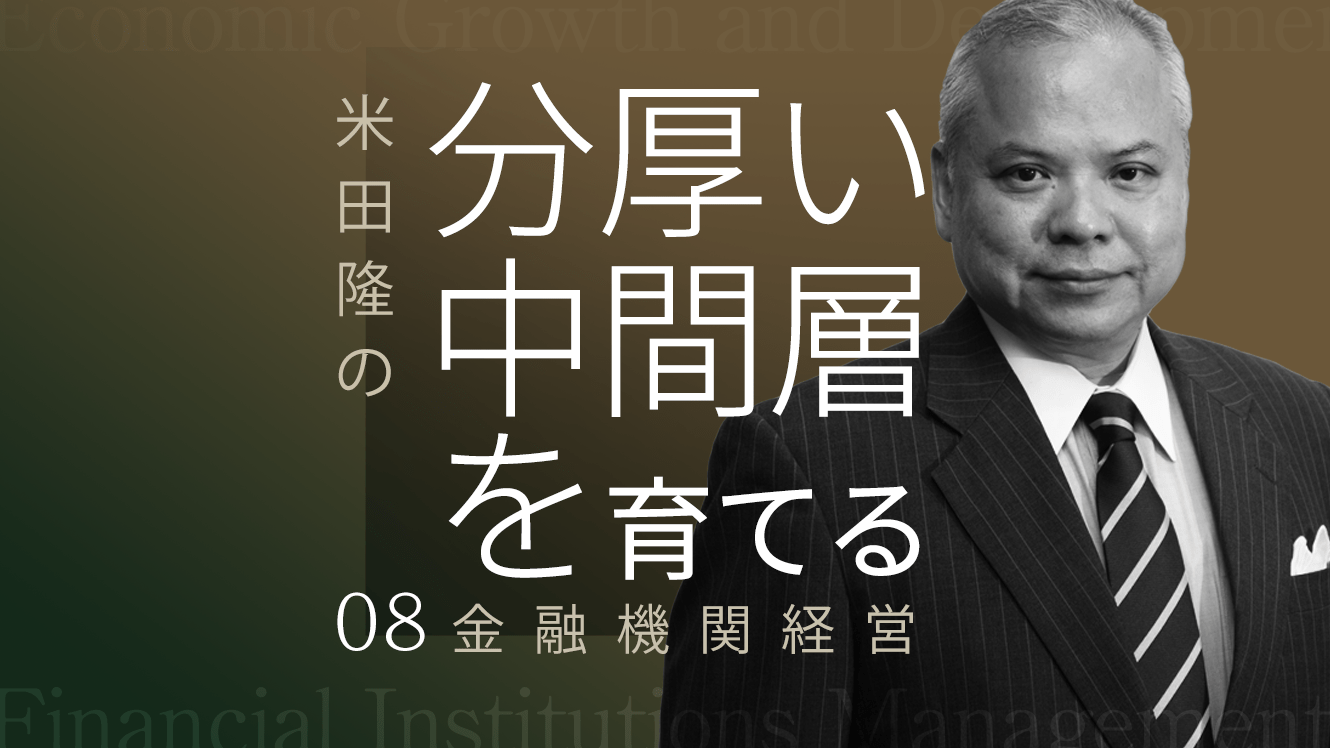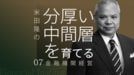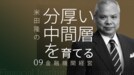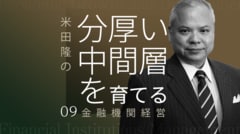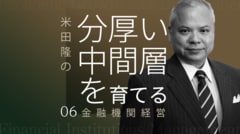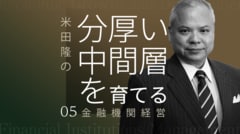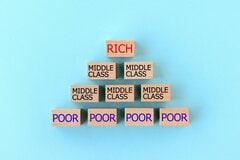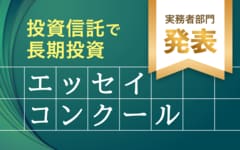株式とは「持ち分」であるという基本を、誰も教えない
米田氏
岸田文雄政権はNISAを恒久化して非課税投資枠を1800万円まで拡大しました。それは政権の大きな実績であることに間違いはありませんが、少額からでも株式や投信などに投資しやすい制度を整えるだけでは不十分です。「なぜ資産形成が必要か」「分散投資の要諦は何か」といった文化資本として中間層に根づいていなければ、せっかくのNISA拡充も「仏作って魂入れず」になりかねません。
蔵元さんは数々の実績を積んでこられた伝説のファンドマネジャーであり、日本の投信業界を知りつくすパイオニア、生き字引でいらっしゃいます。日本の中間層に分散投資という文化資本を広めるには、どうすればよいでしょうか。
蔵元氏
私がフィデリティに入社したのは今から54年前の1969年でした。大阪万博の前年です。同社として初の日本株専門のアナリストを任され、東京事務所を開設しました。長らく日本の資本市場に身を置いてきた者として、政府が「資産所得倍増」や「資産運用立国」の旗を振るのは大変結構なことですが、そもそも「『投資』と『貯蓄』とはどこが違うのか」、「金融資産の中心にある株式とは何ぞや」という基本中の基本を、一般の国民だけでなく、NISA拡充を推進した金融当局でさえも必ずしも十分に理解しているとは思えないのです。
株式というのは要するに「持ち分」です。ある企業の株式を持っていれば、その会社の利益が3割増えると、長い目で見て株価も3割増となり、自身の財産も3割増える――ということです。この「持ち分」という感覚が日本人にはいまだに薄く、同じ金融資産の中で株式と債券の本質的な違いへの理解もあいまいです。それなのに「株式への投資を!」と国民に呼びかけたところで、掛け声倒れに終わるでしょう。
資産運用立国の実現には、国民の金融リテラシーの向上は不可欠で、手広く施策を打つ必要があるでしょう。ここは政府に頼るだけでなく、企業にはDC年金の加入者や従業員向けの投資教育を担ってもらい、金融業界には分かりやすい商品説明を徹底してもらうなど、民間でもさまざまな努力ができるはずです。

米田氏
株式を発行する企業側にも、自己資本コストへの意識が希薄だったように見受けられます。ある企業が株主総会で「税引き後当期利益の30%を配当する」と決定するということは、「内部留保に回す残り70%の資金を株主の期待利回り以上に増やす」と宣言するに等しいはずです。仮に配当性向を100%にしてしまえば、短期投資と長期投資に本質的な違いは生じません。利益の一部が内部留保という形で企業に再投資されることで、株式の持ち分など(Equity)は個人投資家の視点では売却しない限り、株式の発行企業が時間をかけて成長し続けることができれば、株価が初期投資額からどんどん膨れて大きくなっていくメカニズムこそ、長期投資が短期投資よりも優れた投資法であるといえる前提であるはずです。しかし、内部留保の増加がほとんど現預金の純増になっていては、長期投資も意味をなさず、株式市場としてもPBR1倍をはるかに下回る株価で評価せざるをえません。
その点で蔵元さんは、株主からの期待利回りを上回る利益率を実現するため、果敢に先行投資している企業を、上場直後からボトムアップのアプローチによって1社1社訪問し、それらの企業トップとの対話を十分に重ねた上で選別投資をしてこられました。例えば、往時のイトーヨーカ堂や京セラ、東京エレクトロンなどに始まり、キーエンスやファーストリテイリング、ニトリといった今や日本株を代表する銘柄を「発掘」されてきました。蔵元さんのような目利き力を持ったアナリストがきちんと育ち、その人材が投信委託業界を支える礎となっているでしょうか。
蔵元氏
大事なのは資産運用会社のアナリストやファンドマネジャーが自分のなかに企業分析や証券分析に基づいた確固たる投資哲学を持っているかです。1980年代は「ジャパンアズナンバーワン」とおだてられ、不動産と株式のバブルが発生して値上がりした銘柄の代表格が鉄鋼株と銀行株です。取引企業が互いに株式を持ち合っていて流動性に乏しいため、良好な需給関係を背景に、年々、利益成長率を大きく上回る株価上昇が起こりました。
その時代、私は鉄鋼株や銀行株には頑として投資しなかった。あまりに割高だったからです。その結果、私の運用成績は日経平均に劣っていましたが、それは一時の負け。ほどなくしてバブル相場の崩壊と共に鉄鋼株も銀行株も暴落しました。このような苦い経験への反省を基に、IR協議会や日本証券アナリスト協会が中心となって、上場企業の「情報開示」が格段に強化され、アナリストの育成も一段と進みました。このような努力の積み重ねで、今の資産運用会社の中核には多数の専門知識を持った人材が育ちつつあります。
米田氏
株式バブル絶頂期の1989年10月の世界の時価総額ランキングで1位だったのは、私が当時勤務していた日本興業銀行です。あの当時に銀行株を外すと決断するのは、すさまじいほど徹底した合理性に貫かれていないとできない行動です。ところで、政府から海外の運用会社を誘致することはどのようにお考えでしょうか。最も早く日本に進出した外資系資産運用会社の1つであるフィデリティが、初めて採用した日本人ファンドマネジャーでもある蔵元さんのご意見をお聞かせください。
蔵元氏
政府は多様な海外運用会社の国内誘致に乗り出していますが、私は歓迎します。それによって国内外の資産運用会社の間で競争が激化し、その結果として、各運用会社がそれぞれの運用哲学に基づいて提供する商品のラインアップが多様化され、更に運用成績も向上すれば、ファンドを選ぶ側にも多様性が生まれ、その成果は全て投資家に帰属し、投信市場の活性化につながるでしょう。
投資の基本は目先の利益ではなく再投資による複利効果を狙うこと
蔵元氏
「再投資」は英語だと「Plowback」と言いますね。生えてきた麦や豆の全てを刈り取ってしまうのではなく、その一部を畑にすき込むという意味です。目先の利益確定を急ぐよりも、複利効果で一層の収益を生みだす土壌を育むべきです。よく「日本人は農耕民族だから投機を嫌う」などと言われますが、私は必ずしもそうは思いません。なぜなら日本人の多くはかつて投機に走ってきた歴史があるからです。現在の多くの日本人は、バブルの後遺症で投機のみならず投資そのものにも慎重になっているだけです。それに日本人の発想が本当に農耕民族的であるならば、Plowbackが根づかないのはおかしいですよね。
米田氏
日本の投資信託業界はDCの普及やNISAの拡大などもあって、着実に投資家の裾野を広げてきたと思います。分厚い中間層を再生するために、投資信託という商品の果たす役割をどのようにお考えですか。
蔵元氏
先ほどから私は私自身の成功事例に触れていますが、同時に多くの失敗も経験しました。20年、30年もたてば業態も大きく変わっていきますから、ある企業だけでなく業界そのものが傾くことも往々にしてあります。個々の株式への投資での成功は結果論に過ぎません。その点、投資信託という商品の救いは、銘柄分散の仕組みが組み込まれているところにあります。
顧客のライフプランに合ったサービスを提供する観点からも、投資信託ほど優れた商品はありません。顧客のニーズはさまざまであり、家族のかたちも、子供の教育費も両親の介護費もそれぞれですね。必要なお金の額も、時期も三者三様です。ファンドマネジャーが良い商品を多数用意すれば、その中から経験豊富なIFAなどが1人1人の顧客にふさわしい商品を選ぶことが容易になります。
また、投信であれば日本と違った経済ステージの国への投資も容易です。海外資産を持っておくことも重要な分散投資です。ただし、その際に個人投資家の方々は、直接個別の株式に投資する場合には、個々の海外企業の業績動向や競争環境などを常にチェックしなければならず、それは大変な負担になります。その点、海外市場の現状を熟知し、多くの海外企業を常にチェックしているファンドマネジャーが運用する海外の投資信託であれば、個人での運用よりもさまざまなリスクを軽減しながらリターンを享受することができるでしょう。加えて、国、地域、銘柄ごとに十分に分散している投資信託で運用することができればなお良いでしょう。
金融機関や資産運用会社の役割 ~個人の金融リテラシーの向上に役立つこと~
米田氏
若い人の誰もの実質賃金が上昇する20~30歳代の15年~20年間で、投資信託の特性を活かし、毎月の給与の一部を積立・分散・長期で投資することが、日本の中間層の劣化を資産形成面から防いでくれます。こうした考え方を広めていくには、もちろん投資信託のプロダクトサイドや流通サイドの役割は大事ですが、より大切なのは各家庭のなかで長期投資がいかに重要かを伝承していくという、資産運用における「文化資本」の承継ではないでしょうか。
蔵元氏
その通りです。そのため、金融機関や資産運用会社、さらにIFAも加えてできる第1の貢献は、各家庭の金融資産の一部を形成する長期投資の習慣を支援することです。私が今でもよく見る夢は運用に失敗した夢なんですよ。一方で、これまでの人生を振り返ってみると、先ほどお話したようなアプローチによって、投資先が10年、20年後に大きく成長したことは大変喜ばしく、投資の醍醐味だと感じています。
これからの私の使命の1つは、こうした投資の醍醐味を若手のアナリストやファンドマネジャーに伝えていくことだと思っています。したがって、一般投資家への啓蒙ではないかもしれませんが、アナリストやファンドマネジャーの育成によって、彼らが運用する金融商品の成績が上がれば、顧客の運用資産残高も増加します。その結果、資産運用のメリットを一般投資家の方々も実感し、各家庭で資産運用に取り組む良い刺激になるでしょう。
日本には20万人以上のIFAがいると言われていますが、これまで話してきた長期投資を支援できる独立系IFAを今後さらに増やしていくことが重要です。そのため、米田さんが話される「伴走者としてのIFA」の価値は大きく、その育成も大事にしていくことが必要だと思います。伴走者の水準向上なくして、個人の金融リテラシーの向上はありません。個人だと、どうしても恐怖や欲に駆られて短期売買に走ってしまいがちです。顧客の伴走者として客観的に、そして冷静に助言できるような、そういうIFAなどのアドバイザーを育てることも欠かせません。