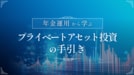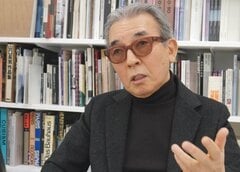ファンド選定にあたって押さえておきたいポイント
具体的な内容は連載第2回以降の資産クラス編で説明しますので、ここでは筆者の私見になりますが、一般的な原則論をお話ししたいと思います。
日本で金融法人や年金が採用しているPAの主要資産クラスとしては、インカムの獲得を主とした実物資産の不動産やインフラ、さらにはPDの他に、キャピタルゲインを主として高いトータルリターンの獲得を目指すPEの4種類があります。
また、実物資産の運用戦略は、稼働中資産からのインカム獲得を目指すコア型、稼働中資産からのインカムに加えて割安で購入した資産をバリューアップしてキャピタルゲインを獲得するバリューアッド型、ファンドの主要なリターンの源泉がキャピタルゲインになるオポチュニスティック型に分類されます。コア型とバリューアッド型の両方の特性を兼ね備えたコアプラス型も存在します。
PDの主流である中堅企業向けの融資であるダイレクトレンディング(以下DL)でも、最上位のシニアローンに特化した戦略、シニアローンに劣後するメザニンローンを一定程度取り入れた戦略に加え、経営破綻に直面した企業に対する債権を割安で購入するディストレスト戦略もありますが、当該戦略はリスクが極めて高いので日本ではまだ一部に止まっているようです。
さらにファンドのタイプとしてファンド期間に定めがなく途中解約が可能なオープンエンド型と、定められたファンド期間内において途中解約が認められないクローズドエンド型の2つがあります。さらに不動産やインフラのような実物資産では、資産の持ち分を取得するエクイティ投資のほかに、不動産やインフラに対するローンに投資をするデット投資があります。これらは図表3「プライベートアセット投資の選択肢」にまとめてみました。
図表3 プライベートアセット投資の選択肢
さまざまなタイプのファンドの中からどれを選べば良いのでしょうか。これはポートフォリオが期待するリターン水準やリスク、あるいはPA投資に対する経験の度合いによって変わってくると思います。初めてPAに投資をするのであれば、まずはインカム系の資産クラスから、不動産やインフラのような現物資産であればオープンエンドのコア型ファンドから始めるのが良いと思います。不動産やインフラは耐用年数が数十年と長いので、バイアンドホールドのオープンエンドに適した資産クラスです。またオープンエンドの場合は投資を実行する際にファンドが保有する資産の全容を把握できるので、保有資産の地域分散、セクター分散、収益水準等の分析が容易です。なお、同じインカム系でもプライベートデットは、融資期間が契約上は5~7年程度ですが、実際には期前返済により3~5年程度と比較的短くなるので、オープンエンドよりもクローズドエンドの方が適していると思いますし、ファンドの数もクローズドエンド型が圧倒的に多いです。オープンエンド型のファンド数は少ないですがそれなりにメリットはあるので、劣後しているということではありません。いずれにしてもファンド選定の詳細については続編で資産クラス別にお話ししていく予定です。
リスクを理解した上で、じっくり投資を進めることが肝心
視点は変わりますが、一般的な心構えとして「自分が理解できるファンドを選択する」ことが不変の基本原則でしょう。年金の場合にはコンサルタントを起用しているケースが多いですが、コンサルタントの推奨案件でも、自身でリスクの所在が分からないままに投資をしてしまうと、後で「こんなはずではなかった……」となりかねません。
これは安易な考え方かもしれませんが、あるファンドが(自身でファンドの中身がある程度理解できているという前提で)日本国内で相当数の機関投資家に採用されているのであれば、これは「みんなで渡れば怖くない」ということではなく、多数の投資家の目が入っているという点は考慮すべき点であると思います。また、必ずしも信託商品である必要はありませんが、信託商品として販売されているファンドは、各信託銀行がしっかりデューデリジェンスを行っているので、信託報酬の支払いに抵抗がなければ安心感は持てるでしょう(ただし、信託銀行がレビューしているから投資家サイドの分析は適当で良いということではありません)。一方で、信託銀行も数多くあるPAファンドの一部をカバーしているだけなので、信託銀行が提供するラインアップに拘っていると投資機会を見逃してしまうことになりかねません。PA投資に少し慣れてきたらファンド選択の範囲を徐々に広げていくのが良いでしょう。
また、低流動のPAは一度投資をすると後戻りができないという点をよく認識し、慎重に時間をかけて吟味する必要があります。周囲に流されて拙速に判断しないことが大事です。さらに、これは投資家により考え方が異なると思いますが、低流動のPAはビンテージ分散等も考慮するとポートフォリオの構築は2~3年程度の短期間で完成できるものではないので、自分の担当の時代に完結させようと思わず、組織として10年程度の時間をかけてじっくり仕上げていくという考え方の方が良いと思います。Slow and Steadyです。
最近再認識された為替変動の影響
2022年4~6月の急激な円安は、PA投資を行っている国内投資家にも大きな影響を与えました。PA投資の中でも、PEは外国株式と同様、為替をオープンにしている基金が大多数ですが、インフラや不動産等のインカム系ではエクイティ投資でも8割程度の年金が為替ヘッジを実行しています。
PAではいわゆる円クラスのファンドが限られており、大半のファンドでは為替ヘッジを行う場合、(年金は)信託銀行等で3カ月ロールの為替予約を実行します(一般的には「外掛けの為替ヘッジ」と呼ばれています)。2022年4~6月の3カ月間では約12%円安が進行したので、為替予約をロールする際に、為替差損分として年金では時価の12%に相当する追加拠出を求められたようです。外掛けの為替ヘッジを付しているPA投資がそれなりの金額になっていると、手持ちの短期資金では不足してしまい、流動性の高い上場株式や債券のパッシブファンドを一部取り崩す必要に迫られたケースもあったようです。
頭の痛い円ヘッジコストの高止まり
PA投資に限りませんが、為替ヘッジを前提とした資産運用で足元最大の問題はヘッジコストの上昇です。ドル円では約6%、ユーロ円でも約4%のヘッジコストとなっていますが、ドル円の金利差が当面は縮小する気配がないので、年金だけでなく多くの投資家が頭を抱えていると思います。
PA投資でも年金ではインカム系の不動産やインフラ、PDは8割程度の投資家が為替ヘッジを実行しています。為替をオープンにすると6%リターンが改善するとはいうものの、1ドル=150円を超える足元の円安水準から為替ヘッジを外すことは躊躇されるところです(どちらかというと1年先は多少円高になっている可能性がある?)。また年金の場合では為替の変動により資産のリスク量が大幅に増加し、リスクリターン効率が悪化するのでそれは避けたいところです。
一方で、海外不動産は資産そのものが調整局面なので論外としても、コア型のインフラファンドなどはドルベースで9%程度のリターンがあっても、為替ヘッジ後では円ベースのリターンは3%に低下してしまいます。ではもう少しリターン水準の高いバリューアッド型のファンドにシフトするか? これもリスク量をさらに取りに行くことになりますし、PA投資の場合ファンドの入れ替えは簡単ではありません。
ヘッジコストも未来永劫この水準ということではなく、おそらく今がピークで2025年末には4%程度に低下している(といっても、過去の水準と比べると依然として高いですが)ことを考えると、長期投資の観点からは基本に立ち返り、主たるリターン源泉がインカムとなっている資産クラスでは粛々と為替ヘッジを継続するということになるかと思います。11月1日のFOMCで公表されたFF金利の予想(ドットチャート)では図表4の通り低下速度が緩やかですが、いずれ円短期金利も若干上昇することも考慮し、ここは我慢のしどころかもしれません。
図表4 11月1日FOMCで公表されたFF金利見通し(数値は各メンバーのMedian)

出所:米FRB
一方で、DL等のPDは変動金利が主体なので投資家のイールドは上昇しており、為替ヘッジをかけてもドル円のヘッジコスト上昇分を吸収し、円ベースのリターンは以前と同じ水準を維持しています(実際には貸し手優位でスプレッドが多少ワイド化しているのでその分リターンは改善しています)。そのため、PDはインカム系のPA投資では現時点では一番妙味のある資産クラスと見なされており、人気が高まっています。ただし、投資家にとっては都合が良くても、高金利継続は借り手側にネガティブな影響も懸念されますので、この辺りは次回以降の資産クラス編でしっかり解説していきたいと思います。
さて、第1回ではプライベートアセット投資を始めるにあたっての留意点を簡単に解説させていただきました。次回以降は不動産、インフラ等代表的な資産クラスについて、毎回3人の架空の運用執行理事を登場させ、対話形式でポイントを詳細に、かつ分かりやすく説明していく予定です。