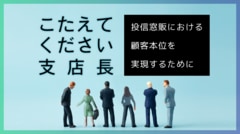──岸田文雄前政権以来、政府が推進してきた「資産運用立国」の一環である資産運用業界の参入促進策が具体的な制度改正に結び付いたことについて、どう見ていますか。
「昨年5月に施行された改正金融商品取引法は、ミドル・バックオフィス業務の外部委託促進と、投資運用権限の全部委託の解禁という2つの大きな柱があります。世間の耳目は、ミドル・バックオフィス業務の外部委託を促進する『投資運用関係業務受託業』という新たな任意登録制度に集まりがちでした。が、私は後者の『全部委託』にこそ、いわば『日本版ファンドマネジメントカンパニー』の設立を可能にする観点で、今回の制度改正の本質があると考えています」
「従前の日本の資産運用ビジネスは、実際に顧客資金を運用するアセットマネジメント業務(高付加価値機能)と、商品を設定したり管理したりといったファンドマネジメント業務(非高付加価値機能)が混在しています。今回の環境整備によって、資産運用会社が、前者のアセットマネジメント業務に集中できる環境整備が急速に進むと期待しています」
「ただ『委託』という表現には、実は違和感を抱いています。『委託』は本来アセットマネジメント会社がやるべき業務の一部を任せるといったニュアンスの強い表現ですが、むしろ、そもそもアセットマネジメント会社が担う必要のなかった業務を外部化する『機能の分化』といった方が正確でしょう」

──ETFを手掛ける事業者をサポートするETFホワイトレーベルのサービスを開始した経緯について聞かせてください。
「2023年の秋頃、ちょうど私たちがファンドマネジメントカンパニーの第1号案件(肥後銀行子会社・九州みらいインベストメンツを投資助言会社とする私募ファンドの設定)を発表したタイミングで、東証側から最初の相談がありました。東証は当時、アクティブETFの解禁を進めていましたが、実際に日本でETFを設定・上場できる運用会社が少ないという現実に直面していたのです。そこで、当社のようなファンドマネジメントカンパニーがETFのファンドマネジメント業務を担うことで、海外勢を含む新興事業者がよりスムーズに日本市場に参入できるのではないかという期待を抱いていたのです」
「これまで海外の運用会社が日本でETFを上場させるには、子会社を設立し、ライセンスを取得し、必要な人員や設備をすべて揃える必要があり、参入のハードルとなっていました。また、従来の制度では、ヘッジ目的以外でのデリバティブ使用を制限する厳しい運用規制があり、投資会社の持分に関する「3%ルール」などの論点も残っていました。この「3%ルール」は、日本のETFが海外のETFをマザーファンドとする場合、子ファンドである日本のETFの残高がマザーファンドの残高の3%を超えると規制に抵触するというものでした。これらの課題が東証と金融庁の連携によって解決し、今年5月末にファンドマネジメントカンパニーを活用したETFも認められるようETFの上場基準が見直されたことで、ようやくETFホワイトレーベルの本格的な受入態勢が整った経緯があります」
「東証や金融庁も、将来的には当社だけでなく、複数のファンドマネジメントカンパニーが登場し、競争が生まれることを期待しているようです。当社も業界全体の活性化に貢献できるよう引き続き努力してまいりますが、現実的に考えると、すぐに他社が追随するような状況ではないという印象を持っています」
──ホワイトレーベルの取り組みを通常の公募投信ではなく、あえてETFから始めた狙いは何ですか。
「業界全体の生産性を高め、持続可能な発展を実現するためには、抜本的な構造改革が不可欠であり、その意味で、ETFは通常の公募投資信託に比べ、業界構造を比較的変化させやすい分野だと考えられます。特にアクティブETFは、まだ市場として未成熟であり、新たなファンドマネジメントカンパニーのユースケースを築き上げる上で最も適していると判断しました」
「ETFホワイトレーベルが軌道に乗れば、中小規模の運用会社にもサービスを展開したいと考えています。現在、多くの小規模な運用会社は、ファンドマネジメント業務に多大なリソースを割かざるを得ず、運用という本来のコア業務に集中しにくいという課題を抱えています。残高が小さい運用会社ほど有効に機能する当社のサービスを活用いただくことで、経営効率の向上に貢献できれば幸いです」
「より長期的な目線では、大手の運用会社を含め業界全体に『機能分化』の波を広げていきたいと願っています。金融庁がたびたび問題提起しているように、大手は数多くの投信を手掛けているものの、実際に収益の柱となっているのはごく一部という現状があります。もちろん既存の運用会社にとっては、長年培ってきた事業構造を変えることは容易ではありません。特に大手企業は、自社グループ内のファンドマネジメント機能を外部に出すことに抵抗があるかもしれませんし、自社ブランドでETFを展開しているケースも多いため、当社のサービス導入は慎重になるかもしれません。ETFから実績を積み重ね、ファンドマネジメントカンパニーの有用性がより広く認知されることで、中小から大手へと『機能分化』の流れを広げていきたいと考えています」