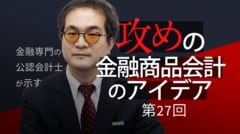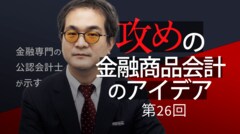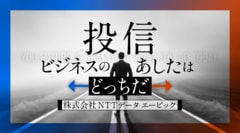① 国債に減損処理が必要ない理由
先月の小欄『国債に減損処理が必要なのか』でも申し上げたとおり、著者自身は、国債(やそれに準じた信用リスクのない債券)については、基本的に減損処理は必要ないと考えている。これについては先月も論じたとおりだが、その要諦を改めて繰り返しておくと、次の通りだ。
● 昨今の金利上昇に伴い、一部の金融機関では超長期ゾーンを中心に、保有している国債などの債券時価が大きく下落している。このため、一部金融機関では国債などの減損処理を迫られているケースもあるようだ
● しかし、現状において、国債の減損は必要ないと考える
● 企業会計基準委員会(ASBJ)が公表する『移管指針第9号 金融商品会計に関する実務指針』(以下実務指針)第91項「時価のある有価証券の減損処理」によると、時価のある有価証券(売買目的有価証券以外)の時価が著しく下落したときは、②「回復する見込みがあると認められる場合を除き」、減損処理(価格下落後の時価を貸借対照表価額としたうえで評価差額を当期の損失処理すること)が求められる
● ただし、円建て債券の場合、この「②回復する可能性がない」場合に該当するのは、信用リスクの増大による時価の大幅な下落に限られる
● 日本政府の信用状況が悪化したことによるものではなく、実務指針第91項が想定する「単なる一般市場金利の上昇」と考えるのが妥当であり、したがって現在のような国債の金利上昇を主因とした時価下落は、減損処理の対象となり得ない
● 諸外国でも利回り3%台、4%台は普通に見られる水準であり、異常値とは言い難く、日本のCDSのスプレッドも日本政府に対する信用リスク増大を意味しているとは言い難い
したがって、結論からいえば、保有している日本国債に関しては、時価が「著しく下落した」場合であっても、減損処理の対象とする必要はないし、また、減損処理すべきでもない。金融商品会計の概念上、円建ての債券の減損処理は信用リスクの増大に起因する場合に限られると考えるのが妥当だし、この「信用リスクの増大」という事象の認定をすることなしに市場価格だけで形式的に「著しい下落」に該当すると判断すると、金融商品会計の適用にあたって実務的な混乱も生じかねないからだ。
② 国債市場の現状
ただ、著者自身が経営する会社には、それ以降もときどき、この「保有する国債の減損処理は必要か?」とする論点に関する問い合わせがある。やはり、形式的に見て「時価の著しい下落」に抵触している場合や抵触しそうになっている場合は、その減損処理が必要ではないか、という疑問が浮かぶのは当然のことでもある。
前回も指摘したが、とくに超長期ゾーンの国債は(回号によっては)取引価格が額面の50%を割り込んでいる事例もある。日本相互証券株式会社ウェブサイトの『BB国債価格(引値)』で確認すると、8月末時点で4銘柄あった。いずれも40年債だ(図表)。
図表 国債の価格(2025年8月最終営業日)

たしかに時価ベースで見ると、金融商品会計にいうところの「著しい下落」(おおむね50%以上)の要件は充足している。これらの共通点は、いずれもクーポンが1%未満の低クーポン債であり、残存年数も30年以上である。
また、図表には記載していないが、「50%以上の下落」には該当していなくても、それに近い下落率を示している銘柄も散見される。
ただし、これらについては単純に、市場金利の問題で説明がつく。国債などの債券の多くは「固定利付債」である以上、価格の下落は将来受け取るクーポン水準が市場実勢利回りと比べて低いことによってもたらされているものであり、実際、会計上もアンダーパー(100円未満の価額)で取得した債券については、額面と取得価額の差額は一般に償却原価法(俗にいうアキュムレーション処理)により受取利息として期間案分される。
③ 日本の債券利回りは危機的水準なのか?
しかも、より冷静になって考えてみると、現在の日本国債利回りがそこまで高いといえるのかは疑問である。もちろん、銘柄によっては、見た目「だけ」は時価が額面の50%を割り込むようなものも散見されることは事実であるが、市場利回りは5年ゾーンで1%少々、10年ゾーンで1.6%前後、20年ゾーンでも2.6%前後であり、30年や40年でもせいぜい3%台に過ぎない。かつての南欧国債危機の時に一部の国で観察された「10年債利回り40%台」といったメチャクチャな利回り水準と比べて、現在のわが国の債券市場における利回りは、総じて控え目である。米国30年債もここ2~3ヵ月はおおむね4%台後半で取引されているが、30年ゾーンで日本国債と比べたらずいぶんと高利回りである。現在の日本の債券利回りを「危機的水準」と呼ぶには低すぎる。債券価格の下落は単純に債券自体が低クーポン銘柄であり、残存期間が長いからに過ぎない。
いずれにせよ、本邦の債券利回りは諸外国と比べても著しく高いとはいえないし、CDSのスプレッドのワイドニング(拡大)も観測されない中で、現状で日本国債の利回り上昇が「日本政府に対する信用のリスク増大」を示すと決めつけるのが難しいことは、債券市場の専門家から見れば常識だ。
④ 「満期保有宣言で減損回避」はいかなる理屈に基づくのか
もっとも、その一方、世の中のすべての人が債券市場に詳しいわけでもない。金融市場やマクロ経済学の知識などを持たない監査チームが「この銘柄、減損処理しなくて良いんですか?」、などと問題提起してくることもあるかもしれないが、時としてそれが困った判断をもたらす可能性には注意が必要だ。ここで紹介しておきたいのが、今年7月始め頃にとある新聞が配信した、次のような趣旨の報道記事である。
● 生命保険会社が保有する超長期債に減損のリスクが迫っている
● XX生命(※記事中では実名)は金利上昇により2024年度に一部の保有債券が減損の基準に抵触した
● 同社は当該債券を売却せずに継続保有することを宣言し、実際の減損処理を回避した
● 別の中堅生保でも一部債券が減損の基準に触れたが満期保有を宣言し処理は免れた
ここで注目したいのが、「継続保有の宣言」ないしは「満期保有の宣言」という用語だ。著者自身、金融商品会計ともう四半世紀お付き合いをしているが、不肖ながら、「継続保有の宣言」または「満期保有の宣言」という用語を見たのは初めてだ。もちろん、「継続保有(または満期保有)宣言をしたら減損処理を免れる」という規定は、金融商品会計基準にも存在しない。
これを、どう考えるべきだろうか。
⑤ 「継続保有していたら減損回避」は理論的にも疑問が残る
あえてこの「継続保有していたら減損処理を回避し得る」を理論的に擁護するならば、「債券価格は市場利回りと残存期間によって決定され、長期債は残存期間が長く、市場価格も下落しやすいが、残存期間が短くなってくれば下落していた市場価格が元に戻る可能性が高い」、といった理屈も考えられなくもない。
ただ、「継続保有していたら減損処理は免れる」とする判断は、理論的にも疑問が残る。繰り返し指摘している通り、(あくまでも著者自身の解釈ではあるが)とくに円建ての債券の場合、減損ルールに抵触するのは信用リスクが増大したときなどに限られると考えるのが妥当だからだ。
前稿でも触れたとおり、企業会計基準委員会・移管指針第9号『金融商品会計に関する実務指針』第91項には、次のような記述が含まれている。
「債券の場合は、単に一般市場金利の大幅な上昇によって時価が著しく下落した場合であっても、いずれ時価の下落が解消すると見込まれるときは、回復する可能性があるものと認められるが、格付けの著しい低下があった場合や、債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にある場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められない。」
やや曖昧な文言ではあるが、これについて著者自身は次のように(文言を補って)解釈することにしている。
ケース①債券の価格下落が単純に一般市場金利上昇のみによりもたらされている場合
⇒当該債券を所有し続ければ、満期が近づくにつれて時価の下落は解消し、100円(パー)に向かって戻ってくるため、「回復可能性があると認められる」。
ケース②債券の価格下落が債券発行者の信用リスク増大を主因として発生している場合
⇒当該債券を所有し続けても、満期が近づけば時価の下落が解消するという保証はないため、時価の著しい下落に該当する場合は減損処理が必要である。
⑥ 「得体のしれないリスク」が含まれている債券の継続保有
こうした解釈が妥当であるならば、実務指針上、単なる一般市場金利上昇を理由に減損処理を適用することはむしろ理論的に見て難しい。
逆に、「いかなる場合に減損処理が適用されるのが妥当か」というアプローチで考えるならば、やはり国債などの債券を減損処理の対象とするためには、市場金利以外の何らかのリスク(例えばわかりやすいのはケース②でいう「信用リスク増大」)が必要と見るべきであろう。少し意地悪な言い方をすると、減損処理をする以上、その対象銘柄の減損に値する理由、言い換えれば「金利以外の何らかのリスク(例えば信用リスク)が増大した」とその会社(か監査人)が判断した、と見るべきである。こうした見方に立脚すれば、某紙が報じた「満期保有の宣言」とは、そんな「得体の知れないリスク(?)が含まれている債券を満期まで保有する」ということにならないだろうか?
もしそうだとしたら、なぜその「(金利上昇以外にその債券を減損処理するに値する)得体の知れないリスクを抱えた債券」を「満期まで保有すると宣言」したら減損を免れるのだろうか? このあたりのロジックについては、よくわからない(保有を継続すればさらに金利が上昇して含み損が拡大する可能性もあるだろう)。
いずれにせよ、前稿の繰り返しになるが、一部国債銘柄の時価が大きく下落していることは間違いなく、この点については現実にロスカットルールなどを適用すべきかどうかという議論が生じていることは間違いない。また、「その他有価証券」の保有目的区分で保有している場合、時価評価差額が「純資産の部」に表示されるため、見た目の純資産が棄損することも否定できない。
しかし、その問題と「会計上の減損処理の取扱い」という論点は混ぜるべきではないし、両者は全くの別論点である、という点については、改めて指摘しておきたいと思う次第である。