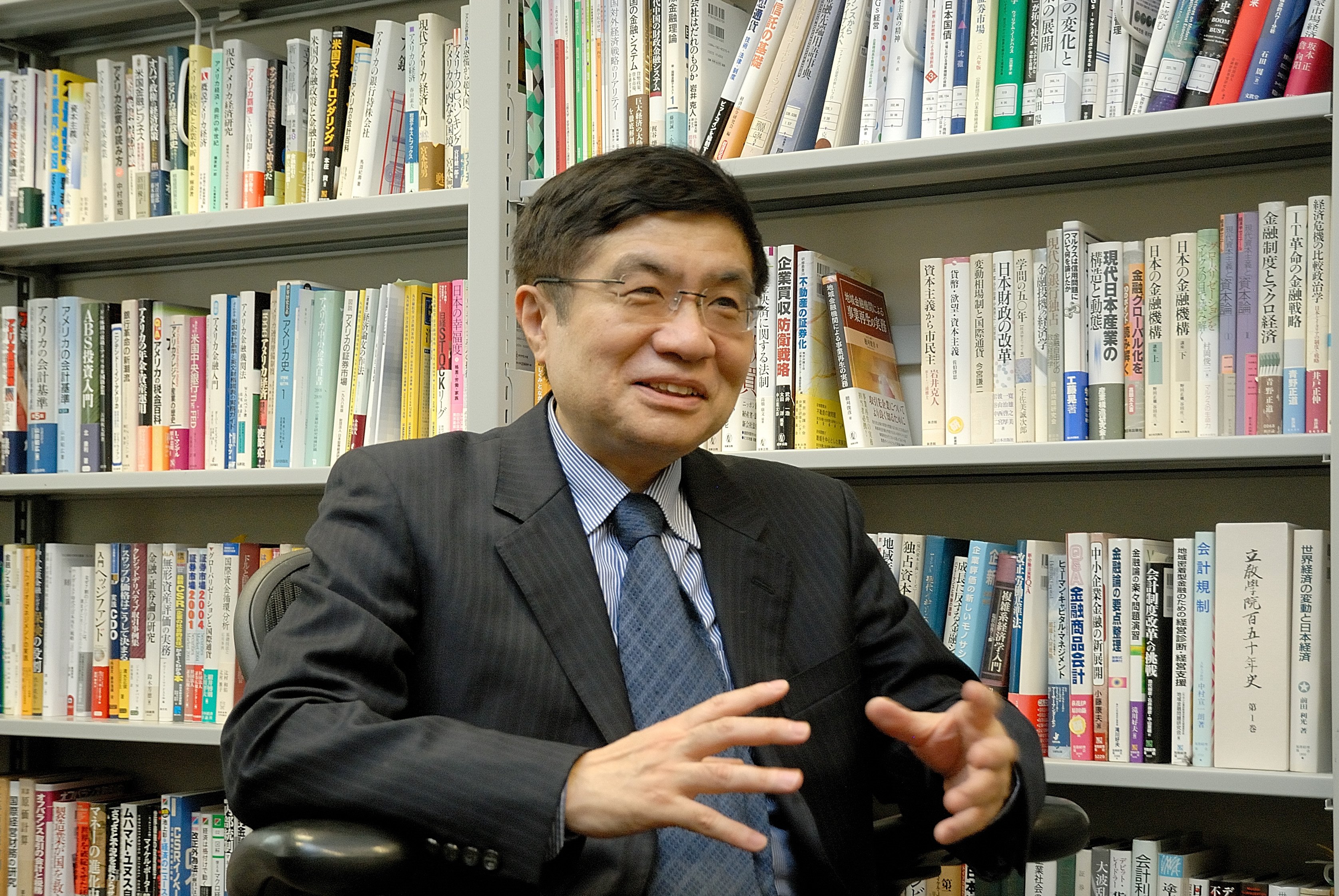大恐慌の失敗を経て、1940年代に基盤が固まった米国の投信市場
――米国では投信に約100年の歴史があります。なぜ米国でここまで発展したのか。歴史的に大きな出来事は何だったのでしょうか。
投信が誕生したのは1860年代の英国です。当時、大英帝国として世界中に進出するなかで、本国から海外への投資も拡大していきました。ただ、多くの個人には、海外についての知識はありません。そこで専門家に資金を預け、専門家が現地の状況などを分析しながら資金を分散して投資する。投資家の財産保全を重視しながら規模を拡大していった――これが投信の始まりです。
ところで、「投資信託」は米国では「投資会社」と呼ばれ、会社形態をとりますが、この英国で生み出された「信託=トラスト」という考え方は、委託者から預かった大事な資産を受託者がきちんと保全するという意味合いがあり、歴史的に、受託者の責任として、預かった資産を慎重に管理していかなければならないという考え方が重視されてきました。投資信託の本質に、このような「トラスト」の理念があることはぜひ覚えておいていただきたいです。
――そして、米国に上陸したのですね。
米国に移入したのは1920年代です。このころの米国の投信は会社形態のクローズド・エンド型で、かつレバレッジの効いた証券が人気でした。そこに1929年、大恐慌が起きます。レバレッジが“あだ”となり、多くの個人投資家が大損害を受けました。
ただ、ここからが米国のすごいところだと思いますが、なぜこうした大惨事が起きたのかを議会で徹底して調査・分析を行い、それらを基に法規制が整備されていきました。
当時、「ブルースカイ法」という州ごとのルールはあったものの、連邦全体での規制が必要だとなり、1933年から1934年にかけて、「証券法」や「証券取引所法」が相次いで制定され、株式市場を監視・取り締まるためのSEC(証券取引委員会)も1934年に設立されました。
仕上げに「投資会社法」が1940年に成立します。この投資会社法は、マーケットの在り方を大きく規制した法律で、現行の「法規制によって投信市場を支えていく」構造がここで出来上がったのです。
この構造のもと、戦後を経て、60~70年代でMMFやCMAの登場といった商品の進化、70年代に従業員退職所得保障法、いわゆるエリサ法や、IRA(個人退職勘定)が創設されるなど、年金・退職金に関連する制度も整備され、今日に至るまで発展してきました。
――米国というと、「自由」を尊重するイメージが浮かびますが、戦前からさまざまな規制が存在していたのですね。
自由競争のためには、ゲームがうまく機能するように、場をどう作るのかが重要です。またルールを定めておしまい、ではなく監視・監督も必要でしょう。
さらにそのためには調査・情報も欠かせないはずです。その点、米国は情報開示も徹底しています。私は以前、米国議会の証券法制に関する調査資料を研究するために、上院議員専用の米議会図書館に何週間か通ったことがありますが、米国では、さまざまな情報の閲覧やオープンな利用を非常に重視し、日本とは決定的に違うと実感しました。
――特に70年代からでしょうか、ごく普通の労働者が投信の進化に「ついていった」のもポイントな気がします。
家計の資産形成手段として、投信が広く受け入れられたのは米国の株式市場全体が長期的に大きく上昇し続けたのが大きな要因でしょう。
1980年代に1000ドル台だったダウ平均株価が、2000年には約1万ドルになり、さらに2020年代には3万5000ドルを超えたりしたわけですから、短期的には上下の価格変動はあっても、「長期的に、株式あるいは投信に投資しておけば確実に資産が増える、合理的な資産形成手段である」という社会的な信認が国民全体に広がりました。まさに株式市場に対する「信頼=トラスト」が重要な意味を持ったわけです。
日本ではバブル崩壊以降、投資から距離を置く個人が多い一方、米国では金融危機が繰り返し発生しても、株価の持続的な成長を支えるさまざまな経済政策や、新しい企業の誕生と成長を促すエコシステムが形成されていたことが、株式市場の社会的信用を高めていたと思います。