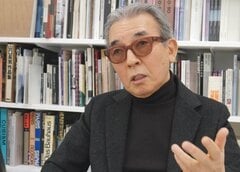①「柔構造化」とは?
ディスカッションペーパー(以下「DP」)とは、目まぐるしい環境変化への対応が急務でありながら、性急な法制度変更には慎重さも求められるようなテーマに対し、当局として論点を整理することで業界とのコミュニケーションのきっかけを作るものです。最近では、AI分野においても同様の目的でDPが公表されています。
現状、暗号資産に関係する規制は主に資金決済法がベースとなっていますが、足元では金融商品取引法(以下、金商法)に移行する案が浮上しています。一方、金商法は資金決済法に比べて規制が厳しいとされており、暗号資産に対して一律にルールを追加すればイノベーションの可能性が阻害されるといった懸念もあります。
そこでDPでは、暗号資産を2つの類型に分けた上で、それぞれの特性に応じて柔軟に規制をかける方向性を提示しています。
具体的には暗号資産を、資金調達や事業活動のために発行される「類型①」と、それ以外の「類型②」に区分。類型②にはビットコインやイーサ(イーサリアム)が含まれるので、要するに、一般的に暗号資産と言われてイメージするものはたいていこの「②」に当てはまることになります。
DPでは断定的な表現を避けつつ、特に流通量が比較的少ない「類型①」についてはより規制が緩い枠を設けた上で、全体として暗号資産分野の参入規制などについて緩和的な類型を設定する可能性を示唆しています。
②インサイダー規制導入には前向き
暗号資産は金商法におけるインサイダー取引規制の直接的な対象とはなっていませんでした。海外で珍しくなくなってきた法執行事例を踏まえ、DPでは暗号資産の取引を新たに規制対象とする方向性に言及しています。
ただ、既存のインサイダー取引の定義は主に上場企業が発行する株式を念頭に置いているため、「重要事実」や「内部者」といったベースとなる概念の範囲を暗号資産の特性に合わせて修正する必要がありそうです。DPでは規制強化を前提として、具体的な制度設計については複数の選択肢をテーブルの載せて慎重に議論を進める考えを示唆しています。
当局は基本的に、規制のアービトラージ(国ごとの規制のズレが生み出すビジネス環境の歪み)を避けるため、制度整備にあたっては国際的な動向に足並みをそろえることが大前提です。しかし、ことインサイダー取引規制に関しては、そもそも国ごとにセーフ/アウトの線引きがまちまちな分野でもあり、金融審内で議論の注目度はそれなりに高まりそうです。
③「家計資産に資するオルタナ投資対象」に
与党が昨年末の作成した税制改正大綱では、一定の暗号資産を「広く国民の資産形成に資する金融商品」として業法で位置づけるという記載が盛り込まれました。DPでも暗号資産が個人投資家を含めて、分散投資の対象として認識されつつある状況に言及。金融庁が実施した投資家の意識調査で、投資経験のある国内個人投資家の暗号資産保有率が一定の割合を占めていることや、米国において、ビットコイン現物ETFに投資する機関投資家が増加しており、公的年金など長期保有を前提とする投資家を含め活用が拡大している現状を紹介しています。
また、投資のリスクは「高いものと考えられる」としながらも、「例えばビットコインは株式等の伝統的資産との相関性が低い」「インフレ耐性があるため分散投資の対象となり得る」といった声を紹介。「特に家計においてはリスクを十分に理解し、投資余力の範囲内であることが肝要であるものの、暗号資産は資産形成に資するオルタナティブ投資の対象となり得るものであり、投資家のリスク選好に応じて一部の資金を暗号資産に分散投資することも考えられる」と記しています。
金融庁はDPについて6月10日までパブリックコメントを実施し、具体的な規制のあり方を検討していく構えです。