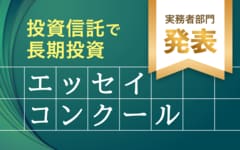今年の5月9日に発足した、全国44行の地域金融機関が参加する「バランスシート・マネジメント・コンソーシアム」(以下、BSコンソーシアム)。その第一回全体会議 兼 創設記念イベントが7月4日に開催された。
BSコンソーシアムは、預金金利推計方法の高度化やコア預金モデルの改善といった資産負債管理(ALM)の高度化を目指し、全国の地域金融機関と専門家が協力しながら共同で検討・研究を行うものだ。
BSコンソーシアムのきっかけとなったのは、静岡銀行の取り組みだ。同社では、「金利のある世界」が到来している中、いかなる環境下においても円滑な資金供給を行う地域の金融インフラとしての役割を果たすため、2024年9月に新たなコア預金モデルを導入した。
当モデルは、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン(以下、アリアンツGI)、NSファイナンシャルマネジメントコンサルティング(以下、NSFMC)、金融工学の権威である木島正明氏との共同研究を通じて研究・開発されたもので、月次の預金残高の変動率に金利局面(上昇・低下)トレンドや季節要因、セグメント間の相関性等の個別パラメータを加味して、将来の預金残高を推計できる。
BSコンソーシアムでは、この取り組みをさらに発展させ、地域金融機関の垣根を越えて協力しながらさらなるALMの高度化を図る。募集時の上限であった30行を大幅に超える44行の応募があり、当初の予定より規模を拡大しての始動となった。
環境変化に対応したALMが今後の金融機関発展のカギ
当コンソーシアムは、金融庁のリスク分析統括課で大手銀行モニタリング室長を務める佐藤雅之氏の基調講演、NSFMCやアリアンツGIからの報告、静岡銀行のリスク統括部リスク統括グループ長の川原幸一氏、七十七銀行のリスク統轄部課長の小関博人氏、木島正明氏を交えたパネルディスカッションなどが行われた。(基調講演とパネルディスカッションは9/8に詳報を公開予定。)
NSFMCの常務執行役員の田幡和寿氏からは、同社が試算したコア預金モデルの結果と今後の課題について共有された。近年、金利の正常化や人口動態の変化など金融機関を取り巻く環境は大きく変化している。同社のコア預金モデルは、こうした変化に対応し、流動性預金残高の増減率を金利局面別に設定。さらに、季節要因や顧客属性も反映している。
複数の金融機関にて同モデルを用いた試算の結果、同じボラティリティやベース増減率に対して、金融機関ごとにデュレーションに1年以上の差が出る場合があるとわかった。さらに、各金融機関で金利局面による残高増減率にも違いがあったと田幡氏は解説する。「こうした違いが出た要因については、BSコンソーシアムにて議論が必要だと考えています。特に、セグメント設定の精緻化やコア預金モデルの改良と高度化、さらには活用の議論を深めていければと思います」。
アリアンツGIの投資ソリューション部長の神頭大治氏からは、金融機関を取り巻く経営環境の変化と戦略的バランスシート経営の重要性について説明があった。
地域金融機関では、人口の減少や投資の活性化により預金の減少が予想されている。アリアンツGIが行ったオンライン調査では、1400名の回答者のうち45.9%がネット銀行で口座を開設したと回答。ネット証券での口座開設数もコロナ禍以降急増し、2023年度には3500万口座を超えた。家計における金融資産の割合も増加傾向にある。
神頭氏は、「預金獲得が困難な今、粘着性の高い預金を効率的に取得し、リスクキャパシティの範囲内で戦略的な資産配分が求められているといえるでしょう。これまでは既存の負債と資本構成を前提とした一方通行によるリスク管理が主流でしたが、今後は収益目標を出発点として戦略的に資産配分計画を策定し、必要に応じて中長期的にリスクキャパシティを構築する双方向的なアプローチが必要です」と課題を提起した。
BSコンソーシアムの今後の展開
当コンソーシアムは8月以降、偶数月の第1金曜日午後3時からを基本とし定期的に開催される予定だ。
次回8月1日の第2回会合では「数理モデルと銀行経営」をテーマに木島正明氏が講演。10月10日の第3回では「新しい預金モデルの開発と導入」について静岡銀行の事例が紹介される。また11月6日には役員向けの特別イベントも計画されている。
コンソーシアムの事務局を務めるアリアンツGIの神頭氏は「この会を決して一方通行の会議にしてはいけないと思っており、双方向で進めていきたい」と述べ、参加各行からのフィードバックや要望を積極的に取り入れる姿勢を示した。
金融環境の変化が加速する中、地域金融機関の連携によるこの取り組みがどのような成果をもたらすのか、今後の動向に注目だ。