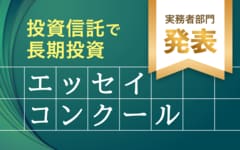今年の5月9日に発足した、全国44行の地域金融機関が参加する「バランスシート・マネジメント・コンソーシアム」(以下、BSコンソーシアム)。その第一回全体会議 兼 創設記念イベントが7月4日に開催された。
その第二部ではBSコンソーシアムに関するパネルディスカッションが行われ、静岡銀行 リスク統括部リスク統括グループ長 川原幸一氏、七十七銀行 リスク統轄部課長 小関博人氏、コア預金モデル「木島モデル」の開発者である木島正明氏、NSファイナンシャルマネジメントコンサルティング(以下、NSFMC) 常務執行役員 田幡和寿氏が登壇。モデレーターはアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン(以下、アリアンツGI) 投資ソリューション部長 神頭大治氏が務めた。その模様をお届けする。
※part.1ではBSコンソーシアムの概要、part.2では金融庁による基調講演をお届けしています
コア預金モデル開発の経緯
神頭:今も多くの金融機関で採用されている「木島モデル」を開発したきっかけについて教えてください。
木島:「木島モデル」の論文をジャーナルに発表したのが2007年4月ですから、研究を始めたのは2006年ころです。きっかけは、当時とある証券会社に勤めていた友人から「コア預金のデュレーションを長くしたいが、どうすればいいか」と相談を受けたことでした。
彼は、デュレーションを長くできれば、多くの地方銀行が国債を買いやすくなり、銀行、財務省、証券会社の「三方よし」になると。社会貢献性が非常に高いプロジェクトだと説かれ、引き受けることにしました。
しかし、いざ始めてみると、私が提案した米国流のモデルは「難しすぎる」とことごとく却下され、途方に暮れました。そこで原点に戻り、流動性預金の残高データを見てみたのです。金利が自由化された1994年時点で10%程度だった流動性預金の割合が、2005年には約30%にまで増えていました。これは低金利を背景に定期預金からシフトしたことが主な理由です。
この時、監督官庁が懸念しているのは、金利が上昇した際にこの流れが反転することだろうと考えました。このトレンドの逆転という発想が鍵でした。
このシンプルな考えをもとに、簡単で使い勝手のいいモデルを組み立てることができました。20年前に問題視していた金利の上昇が今まさに起ころうとしている点は非常に興味深く感じています。
神頭:コア預金モデルにはさまざまな種類がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
田幡:業界の共通認識として持っている明確な類型はないかもしれませんが、計算方法で言えば、解析的に計算するモデルとシミュレーション的にパーセンテージを算出するモデルの2つに大別できるかと思います。
また、使用するパラメータの観点では、「金利局面と預金残高の変動を関連づけているか」や、「GDP成長率などのマクロ経済指標をどのくらい織り込んでいるか」といった分類が可能です。金融機関にとっての経験的または実務的な納得感という観点からは、金利局面と預金残高の変動をどう関連づけるかがコア預金モデル構築や選択のポイントになると考えています。
金利上昇への不安がコア預金モデル高度化に取り組む背景
神頭:BSコンソーシアムのきっかけとなった静岡銀行でのコア預金モデルの高度化は、どのような経緯で開発が始まったのでしょうか?
川原:2024年の9月から新しいコア預金モデルを導入しましたが、その数年前の2022年初頭から開発の検討を始めていました。しかし、当時は米国の金利が上昇するかどうかという時期で、日本での金利上昇は可能性すら業界の中で検討されていない状況でした。複数のベンダー・コンサル会社様に連絡しても、「既存モデルで皆さん満足していますよ」、「システムのアレンジする予算がありません」という回答がほとんどでした。
それでも、将来、金利のある世界が来た時のために、準備だけはしておきたい。そこで、われわれがやりたいことを実現させてくれそうな数少ないベンダー・コンサル会社様と検討を着手しました。最終的に、一番親身に相談に乗ってくれたのが、今回ご一緒しているNSFMCだったわけです。
研究体制では、コア預金のモデルについて私共はアマチュアであることを認識した上で想いを実現するためにそれぞれのプロとしての強みを生かせるよう意識しました。NSFMCはシステム開発のプロで、木島様とアリアンツGIは専門的な知見とグローバルの情報を持っている。自分たちだけではできない領域を補っていただきながら、コア預金モデルの高度化に取り組みました。
純粋にリスク管理を考えるならば、金利のある世界の到来前に金利上昇局面でのリスク管理は優先順位が高くないと思っても当たり前です。しかし、モデルの構築やリスク管理の態勢を変化させるには長いと数年かかってしまいます。このため「今すぐ必要ではない」と考えて行動しないのではなく、出来れば2~3年先の将来を見据えて事前に手を打つことが重要だと考えています。
神頭:七十七銀行では、どのようなリスク管理の取り組みが実施されていますか。
小関:私がリスク管理部署の管理職として配属された2021年末は、米国の金利上昇で外貨建て債券の評価損がクローズアップされた時期でした。当行は幸い影響が軽微でしたが、上司から「これは日本でも絶対に起こるぞ」と言われ、すぐさま経営陣へのレポーティングを始めました。いざ日本の金利上昇が現実になると、当行では外債よりも円債の方が規模が大きいので、対応の難しさに直面しています。
負債サイドに目を向けると、当行が使用しているのは木島モデルです。木島モデルは過去の預金残高に基づいて算出されます。そのため、2011年の東日本大震災の後に預金が急増した影響で、現状では預金のデュレーションが比較的短く、保守的な状況でした。しかし、最近震災後の影響が観測期間から外れ、金利上昇や人口減少、相続預金の増加など外部環境も大きく変わりました。
現在、こうした環境変化に即した新たなモデルの導入に向けて、預金の動態分析を含めた検討を進めているところです。
分析の精緻化が今後の課題
神頭:木島様は、今後の金利リスクやALMのあり方についてどのようにお考えですか?
木島:まず、モデルを一つに決め打ちして、それだけを見ていれば良いという発想は禁物です。私のモデルのように計算が速いシンプルなもので概算を出し、NSFMC様のように時間をかけて精緻なものでリスクを細かく算出するというように、さまざまなモデルを使い分けることが重要です。
ALMで最も重要なのは、負債サイド、つまり預金が将来どうなるかのシナリオをきちんと描き、それに応じて資産サイドのポートフォリオを構築することです。それによって収益が生まれるという認識を持つべきでしょう。
そのために必要なのは「金利の予測」と「預金残高の予測」です。金利の予測は、市場金利と預金金利の連動性を見ればある程度可能ですが、預金残高の予測は非常に難しいです。顧客を年齢や資本金でセグメント分けする方法が一般的ですが、その分け方自体が何十年も変わっていません。社会が変化しているのだから、それに合わせてセグメントも変更する必要があるでしょう。このコンソーシアムを通じて、そうした根本的な部分から考えていくことが、日本の金融業界にとって非常に重要だと考えています。
神頭:最後に、コンソーシアムに対する意気込みをお聞かせください。
田幡:預貸一体管理を進める上で、コア預金モデルは極めて重要です。まずは、どの銀行にも必ずある預金データをきちんと蓄積し、データに基づく行動分析を行うことが第一歩だと考えています。コンソーシアムで皆様からいただくご要望に一つひとつ応え、良い方向に進んでいけるよう尽力します。
木島:20年前と今では、人口減少やデジタル化の進展など、状況は大きく異なります。皆様が定性的に理解しているこれらの変化を、いかにしてリスク管理に使える定量的な分析に落とし込むか。私が長年培ってきたデータサイエンスの知見が本当に使える時代が来たと感じており、この活動を非常に楽しみにしています。
小関:これだけ多くの銀行と協力し合えることを大変嬉しく思います。ALMの分野は専門性が高く、悩みを共有する場も少ないのが実情です。先の見通しが困難な時代だからこそ、このコンソーシアムの意義は大きいです。メンバーとのディスカッションを通じて、課題解決に取り組んでいきたいと思います。
川原:自動車産業は非競争分野でプラットフォームの共通化を進めることでコスト削減を実現しているように、われわれ金融業界も非競争分野では協力すべきです。特にリスク管理においても数多くの課題がある中で、全ての銀行が一から十まで全て自前でやるのは大変です。他業種を巻き込みながら、業界全体で協力することで、現実的に多くの課題に取り組めます。コンソーシアムは皆様の主体的な参加があってこそ成り立ちます。知恵を出し合い、メンバー全員で業界の発展に貢献できれば幸いです。