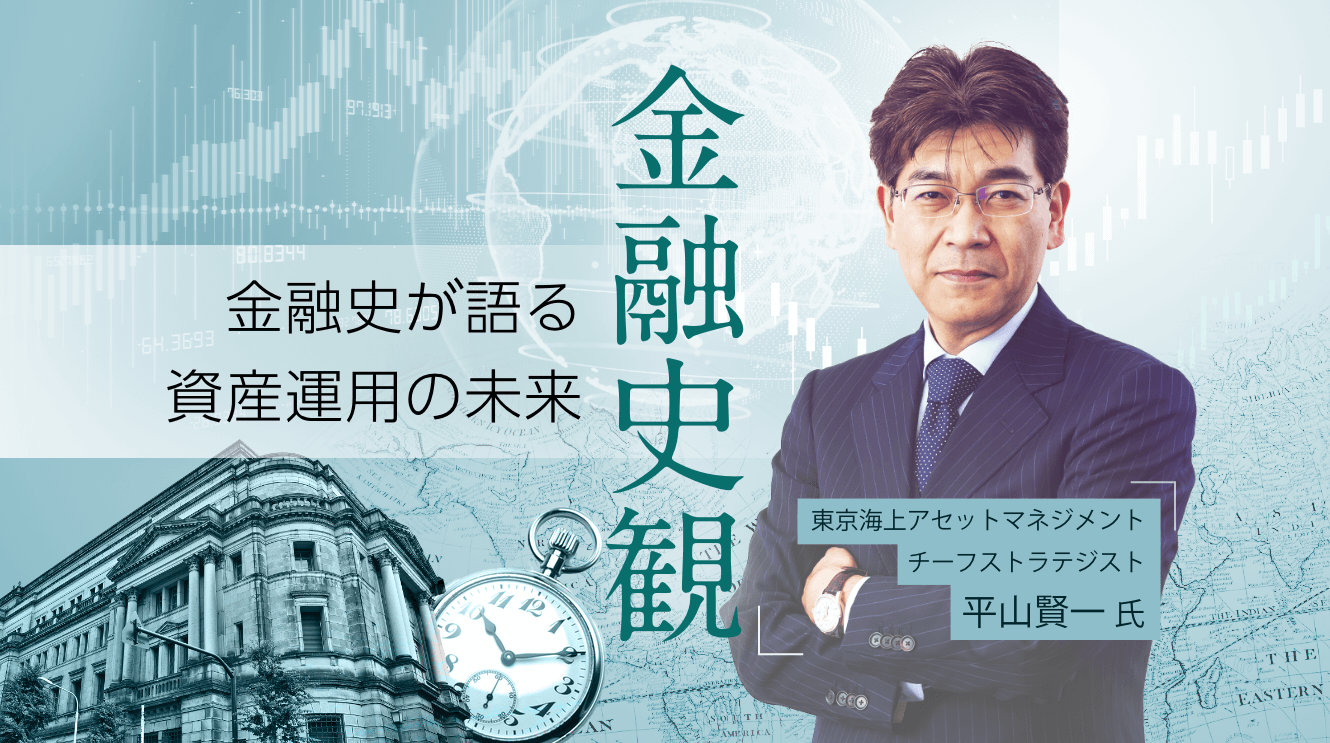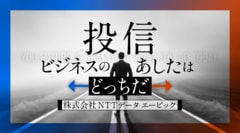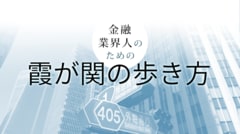前回の寄稿では、現在の不安定な金融市場を落ち着かせる手段が限られているなかで、国家と市場の「蜜月時代」が終わりを迎えていることを、「振り子」の比喩で整理した。では、こうした対立が深まり不確実性が高まる時代において、私たちは個人投資家にどのようなアドバイスを提供すべきだろうか。今回は、国際政治経済の不透明感が強まる中での対応策を、株式・国債・社債といった資産クラスごとに考察したい。
不確実性下における企業選別と株式投資
まず、株式投資についてである。不確実性が増す時代、企業の選別はどのように考えるべきだろうか。
政府による関税強化や保護主義的政策が進むことで、グローバルに展開する大企業はコスト増や売上減少のリスクを抱える。これまで「規模のメリット」を享受してきた企業が、政治的リスクの高まりによって、逆に不利になる「規模のデメリット」を抱えるようになっているのである。自由な貿易を前提に活動してきた企業は、時間の経過とともに、制約の多い経済環境に翻弄されやすくなっているわけだ。大規模にグローバル展開する企業は、小規模な企業よりも相対的に経営上の負荷が高まると言ってよいだろう。
そうした中では、特定の分野で俊敏に対応できる中小企業のほうが、大企業よりも業績上のマイナス面が目立ちにくくなる可能性がある。株式投資にあっては、大型株よりも小型株の方が優位に立つことが多くなるだろう。そのため、時価総額に応じて構成銘柄が決まる時価総額加重平均型の株価指数に連動するパッシブ運用よりも、等比率で構成される株価指数に連動するパッシブ運用の投資成果が魅力的に感じられるかもしれない。2024年にかけての数年間、米国株市場では、「マグニフィセント・セブン」といった超大型株への注目度が高まったが、その偏重は、大きなリスクを抱えていると認識すべきだろう。
また、ブロック化が進むと、原材料だけでなく、労働力(ヒト)やデータといった企業の経営資源の移動にも障壁が生じる。人件費の高い自国での生産への回帰、移民制限によるサービス価格の上昇、サイバーリスク対策など、多方面にわたるコスト増が避けられない。このような不安定性が加速すると、政府は社会の安定を優先し、効率性を犠牲にしてでも介入を強めるだろう。政府による介入や規制は、価格形成の歪みや無駄が放置されがちになるが、それを逆手に取り、ビジネスチャンスへ転換できる企業も現れる。つまり、「歪み」を活かせる企業かどうかが、明暗を分ける時代になるということだ。
こうした局面では、銘柄選別の巧拙によって運用成績の差が拡大しやすいため、優れた選別眼をもつファンドマネジャーによるアクティブ運用が、単なる平均的なアクティブ運用を凌駕する可能性が高まる。もちろん盆暗なファンドマネジャーにはできない芸当なので、ファンドマネジャーの選択にも工夫が必要になるのは言うまでもない。グローバル金融危機のような大変動期に、銘柄選別で成果をあげたファンドマネジャーなどが候補になってくるだろう。
政府債務の拡大と国債市場
次に国債市場について整理したい。そもそも対立と不安定の時代には、政府は景気対策や金融市場の安定化のために借金を増やす傾向がある。中央政府・地方政府を問わず、財源として国債の発行に頼る場面が増えるわけだ。特に主要国では、自国通貨建て国債の発行が中心となり、財政の健全性が後退するはず。
しかし、金融環境によっては国債の消化が進まず、中央銀行が紙幣を発行して購入を支援するような局面も想定される。実際にグローバル金融危機やコロナ禍が、段階的に政府財政を悪化させてきた。そして今回のトランプ政権の自国優先主義の加速は、各地域の防衛費に上昇圧力となってはたらきかけ、財政悪化の第三の波となっている。今後、金融市場が将来的な信用度の低下を織り込み始めれば、償還までの期間が長い長期債や超長期債にリスクプレミアムが付与されるようになるだろう。国債のイールドカーブのスティープニング圧力が高まることになる。中央銀行が再び、長期金利の上昇を抑え込むために、国債を積極的に購入するようになれば、国債の信用のみならず、中央銀行の信認も揺らぐ可能性もある。
財政状態が悪化した国ほど国債の発行が増加するため、時価総額が膨らむ地域の国債には利回り上昇圧力がはたらくだろう。各国の国債時価総額に応じた加重平均型の国債指数は、財政悪化が進む国の債務の比率が高いため、投資成果の足を引っ張るはず。そのため時価総額加重平均型の国債指数に連動するパッシブ運用よりも、世界のGDP規模に応じて国別比率を決めるタイプの運用の方が世界の財政悪化が加速する局面では好ましいのではないか。この場合、手間がかかるが主要国の国別ファンドをGDP比率に応じて保有するという工夫が必要だが、特に米国債や日本の比率が顕著に抑制される一方、中国の比率が高まることになる。
高まるリスクプレミアムと社債市場
地政学的リスクや政治的対立が深まる時代には、人々の不安心理が市場にも反映され、市場の変動(ボラティリティ)が高まる。市場は人間の心理によって動くため、将来の見通しが不透明になると、その不安がさらなる不安を呼び、変動が自己増殖的に拡大することになるだろう。過去の金融危機やコロナ禍においては、世界的な低インフレを背景に、中央銀行が非伝統的な金融緩和策を講じて、市場の動揺を抑えてきた。しかし現在は、インフレ率の下げ止まりや関税強化によるコスト上昇の影響もあり、中央銀行が以前のように市場を支えることが難しくなっている。
その結果として、市場変動の高止まりが続き、投資家はより高いリターン(リスクプレミアム)を求めるようになるだろう。変動が大きい分だけ、それに見合う収益が得られなければ、投資する意欲も下がってしまうからだ。特に、エマージング債券やハイイールド債といった高リスク資産に対しては、2025年春以降、急激にスプレッド(上乗せ利回り)が拡大しており、市場がリスクプレミアムを課し始めている。市場の流動性が一時的に枯渇する局面では、急激な利回り上昇が起こる可能性もあるため、注意が必要だろう。加えて、国家間の対立が金融取引や国際決済にも影響を及ぼし、資金の流れそのものが滞るリスクも高まっている。この場合には、流動性に関するプレミアムも追加的に付与されるため、思いのほかスプレッドが拡大するかもしれない。
ただし、経験的には、社債市場のスプレッドの拡大は急速に進むものの、落ち着きを取り戻す局面は必ず訪れるはず。これまで投資対象にならなかった社債については、魅力的な高いスプレッドを獲得するチャンスが将来やってくる。そのため、気長にその局面を待つべきかもしれない。
以上のように不確実性が増す時代は、これまで常識とされてきた市場指数の構成を見直しつつ、混乱後に市場が落ち着きを取り戻す局面を想定した投資の準備を進める時期と捉えていくことをアドバスしてみたい。