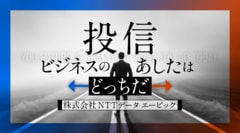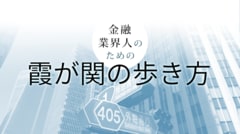金融庁はこのほど公表した「金融行政方針2025」の中で、新たな「地域金融力強化プラン」を年内に策定する方針を表明しています。ワーキンググループは、このプランの具体策を詰める議論を進めるために設置した有識者会議という位置づけです。
初会合では事務局(金融庁)が、地域経済の現状と課題を踏まえて2つの論点を提示。(1)人口減少や少子高齢化が進む地域を支えるために、地域金融機関に求められる役割は何か(2)地域で求められる役割を果たすために、地域金融機関自体の経営基盤をどのように強化していくことが考えられるか――と問題提起しました。
この日のメインは、京都大学経済研究所の森知也氏による、日本の人口減少の将来予測についての基調講演。森氏は、国立社会保障・人口問題研究所による人口推計が「楽観的」であり、実際の日本の人口減少はより深刻なスピードで進んでいると指摘しました。
森氏は、都市と人口の関係を示す「べき乗則」に注目。森氏の予測によれば、現在の傾向が続いた場合、将来的に10万人以上の都市数は大幅に減少し、より少数の、互いに離れた大都市に人口が集中していくといいます。例えば、100年後(西暦2120年)には100万人以上の都市は東京、大阪、名古屋、福岡のわずか4つしか残らないといった可能性に言及しました。
その上で森氏は、厳しい見通しに向き合い、総花的にすべての地域を維持するのではなく、優先順位をつけた上で都市機能を互いに離れた少数の拠点に集約させる「トリアージ」的な考え方の重要性を強調。「全てを残すのではなく、100年先に残る都市から拠点を順位付けし、どこを残し、どこを畳んでいくのか、畳む時にどうソフトランディングしていくか、これこそが一番考えなければいけないのではないか」と述べました。
初会合ということもあり事務局側は、具体的な政策的措置の方向性について直接的な言及を控え気味でした。一方、会合に参加した有識者委員からは、森氏の講演を踏まえ、地域金融機関の力で地域のさまざまな課題を解決する方策について踏み込んだ発言もみられました。広域統合、エクイティによる企業支援、非競争領域での連携といった論点に絞って、当日の議論の流れを整理します。
①県境を越えた「広域統合」の必要性、指摘相次ぐ
ある委員は、「地域金融機関の持続性には難しい問題があり、経営統合という考え方は避けて通れない」との見方を示し、「直近では同じ地域内の金融機関同士での統合が進んでいたが、むしろ隣県やその周辺を含め広域統合をどう進めていくかが非常に大きな問題になっていく。金融機関の規模が大きくなると、企画機能や支援機能も充実してくると思う」と指摘しました。別の委員も「都道府県単位でマーケットを規定する時代はもう終わっている」と述べました。
消費者団体所属の委員は「このワーキングのミッションは、さまざまな支援策を弄して地域銀行を助けることではない」とし、「地域のために地域銀行は何ができるのか、何をやらなければいけないのかという視点に立って、地域で暮らす人々が安心して働ける場をどう作っていくかに本気で取り組む挑戦になるのではないか」と強調しました。
②エクイティによる中小企業支援
また、地域金融機関が融資だけでなくエクイティを通じて企業を強力に支援すべきだといった趣旨の発言も複数委員から聞かれました。
ある委員は「地域の多くの課題を解決したり対応したりするのに莫大なお金が必要であり、しかも中長期的な供給が必要になるのであれば、エクイティを適切に利用することが非常に重要ではないか。単に融資を回収するということではなく、融資先企業が増えていくといった観点での取り組みが重要だ」と述べました。
一方、地域金融機関にコンサルティング機能やM&A支援を求める議論の流れに対し、「果たして銀行自身がこんな機能を持つような人材を持っているのか」と指摘する声も上がりました。
③非競争領域の共同化
この他、有識者委員側からは、サイバーセキュリティなど、非競争領域での連携を推進すべきといった指摘も上がりました。
座長を務める神戸大学経済経営研究所教授の家森信善氏は、会合の終盤、「組織形態・規模は一様になる必要はないと思うが、広域連携共同化や経営統合などによって効率化を進めていくことは不可欠だろう。特に非競争分野でのコスト増については共同化によって効率的に対処できる動きが広がるよう、政策当局としても積極的に対応していただきたい」とした上で、「たとえば合併銀行の遊休不動産の活用など規制を見直すことで、合併や経営統合をより魅力的にするような効果も期待できるのではないか」と話しました。
次回会合は10月2日に行われる予定です。